|
――大丈夫ですよ――
その昔、沖田は少しだけ不満げにこう言った。
――土方さんには、風がついてるから――
不満げに、だけど、どこか羨むように。
――その風があなたを守ってくれるから――
だから、大丈夫なんだと彼は言った。
そんなものあるわけがないとあの時土方は笑ったものだった。
ひゅ――と風が唸った。
それは目も開けていられないような強い風だった。
雪を散らし、
雪を舞い上げ、
風が、
吹く。
そこに存在する全てを吹き飛ばすような、その強い風は、
まるで、
神風――
「がっ!?」
一陣の風が吹き抜けた瞬間、悲鳴が空に舞い上がった。
そして次いで、どさりと、雪の上に何かが倒れる音がした。
雪の上に赤が広がった。じわりと新しい雪を溶かして。
「‥‥え‥‥」
土方は驚きの声を上げた。
刃を振り上げ、今まさに自分を殺そうとしていた男が、雪の上に倒れて、絶命していた。
「な、なんだっ!?」
と敵兵が驚きの声を上げるのは無理もない。
彼は突然、悲鳴を上げて突然倒れたのだ。
なんだ、なにが起こったのかとあたりを見回すばかりである。
そんな彼らの前に、また、風が生まれて、吹き抜けた。
「ぎゃ!?」
驚愕の表情のまま、短い声を上げてまた敵の一人が倒れた。
空に真っ白い粉雪と、真っ赤な血が舞い上がり、それはすぐに強い風で吹き消される。
鋭い風が男を斬ったようにしか見えなかった。
「ひっ!?」
情けない声を上げて一歩退いた敵の身体が、
ひゅ、と唸った風に巻き込まれて、
「ぎゃぁ!」
その胸から血しぶきを巻き上げた。
「っ」
土方も刀を構えた。
鎌鼬‥‥というものが彼の脳裏によぎった。
それが妖の存在の仕業ならば、刀などで応戦できるかは分からないが‥‥それでも、男はやられてたまるかと刀を
構えた。
しかし、
ざん、
「ぐあ!」
ざんっ、
「ひぐっ!?」
風はまるで意志を持っているかのように人々を斬りつけた。
土方以外の人間を。
彼の敵を。
斬りつけた。
そうまるで、
彼を、
守るみたいに――
――土方さんには、風がついてるから――
沖田は言った。
――時には盾となり、時には剣となる風が――
そんなものあるわけがない、と土方は言うけれど、沖田は頭を振って、あなたには風が味方についているんですよと
笑った。
――その風は、あなたを守って、あなたの道を切り開く為に在る――
否、と沖田は言い直した。
――あなただけを――
彼だけを、守り、そして彼だけのために、道を切り開いた。
それはなんだかまるで、と彼は困ったように言った。
――風があなたを愛しているみたいだ――
風は‥‥ただの比喩だと、男は気付いた。
気付いていたけれど、否定も肯定も出来なかった。
何故ならば、彼の傍には沖田の言うとおり‥‥風がついていたから。
どさ――
最後の一人が声さえ上げずに大地に倒れた瞬間、風がぴたりと止んだ。
止んだ瞬間、巻き上げられた白い雪が舞い落ちてくる。
そして、
ふわりと、
その止んだ風の中心にそれが現れた。
今までどうして雪に紛れていたのだろうかと不思議にさえ思う、漆黒の衣に身を包んだその人が。
その人は小さな人だった。
たった一人であっという間に5人を倒したとは思えないほど。
否、あんな強い風を巻き起こすとは思えないほど。
小さくて、華奢な身体をしていた。
その光景はよく、目にしたものだった。
その人はいつだって、突如目の前に現れた。
そう、風の――ように。
「少し見ない内に、腕が鈍ったんじゃありません?」
からかい混じりの声音で、その人は言った。
その声は凛とよく通る、心地の良い声だ。
だというのに、土方の心臓はどくりとまるで嫌なものにでも会ったかのように大きく震えた。
「この程度の敵に遅れを取るなんて、あなたらしくもない。」
だけどその声は、
今、誰よりも心強いと思う人の声で。
今、
誰よりも、
会いたかったと思うその人の、声で。
「‥‥ま‥‥さか‥‥」
土方の口から掠れた声が漏れた。
瞬間、ざあっと再び強い風が吹いた。
目も開けていられないほどの強さだというのに、男は決してその瞳を閉ざそうとはしなかった。
決して逃すものかと、その姿を目に捉えようとした。
風に吹かれて、ばさりと黒の衣が空に巻き上げられる。
その人物の頭を覆っていた黒い布が、青空に真っ白い雪と共に舞い上がった。
そして、
柔らかく変わった風に、はらりと美しい色が落ちる。
木漏れ日を受けてきらきらと輝くのは、美しい金色。
それは静かに舞い落ち、影を落とせば優しい色へと、変わった。
その優しい色は、
男が、
焦がれてやまない、たった一つの色だった。
この世界にたった一つの、
彼が愛した、
色だった。
ま さ か。
乾いた喉の奥で言葉が詰まった。
まさかまさかまさか。
美しい飴色が緩やかに揺れた。
あの頃よりもずっと短くなった髪が、肩口でふわふわと揺れていた。
まさかまさかまさか。
これ以上ないくらいに見開かれた瞳に、
ひゅ、
と風が一陣の塊となって飛び込んでくる。
それに遅れて、
ぱん!
と破裂音が聞こえ、白い雪を何かが舞い上げた。
「いたぞ!あそこだ!!」
男を現実に引き戻す野蛮な怒声が響き、振り返れば銃を構える敵兵の姿が迫っている事に気付いた。
ち、と土方は舌打ちを一つし、即座に立ち上がり、駆け出す。
てめえらの相手をしてる場合じゃねえんだよ――
不機嫌そうに心の中で吐き捨て、ちらりと視線を流せば、しかし、そこにもうその人の姿はない。
――どこへ?
もしやあれは幻だったのだろうかと思った瞬間、
ふいに背後で風が揺れる。
怒号の中で、凛としたその声がひどく大きく聞こえた。
「‥‥あなたの後ろは私が守ります。」
力強く、告げた。
あなたの後ろは自分が守ると。
だから、
「あなたは前だけを見て。」
絶対の自信を込めたその言葉に、土方は身体の奥から力が沸いてくるのが分かった。
それは、
希望というやつだった――
――土方さんには、風がついてるから――
くるくると楽しげに風が踊る。
雪を巻き上げ、枝葉を揺らし、風はふわふわと楽しげに踊る。
その度に短い断末魔と、血飛沫が空に上がり、次々と敵兵は物言わぬ骸へと変わっていく。
彼らを屠るのは、風だ。
何にも囚われない、自由な――風。
沖田は、その人をこう例えた。
まるで、風の化身――
「あなたは前だけを見て。」
その言葉の通り、土方は前だけを見て戦った。
後ろは見なくても良かった。
迫り来る敵は全て、その人が斬り捨てるから。
彼は前だけを見て戦った。
ただの二人きりだというのに、負けない自信があった。
絶対に勝てるという自信があった。
だって、
ここには、
『彼女』がいるのだから。
――もしかして、これは夢なのだろうか?
男は刃を振るいながらふと、そんな事を思った。
これは都合のいい夢ではないのかと。
本当はもう、自分はあの時死んでいて‥‥これは死んだ自分が最後の夢として見ているのではないのかと。
だって‥‥
ここにその人がいるはずがないのだ。
ここに、
自分の傍に。
だって‥‥
自分が、
その人を、
遠ざけた。
いらないと言って、傷つけて、遠ざけたのだ。
それなのに、ここにいて、自分のために戦ってくれているなんて‥‥都合が良すぎるじゃないか。
「ぎゃっ!?」
立ち塞がる敵を斬り伏せると、男の目の前から敵の姿がいなくなる。
背後でどさりと重たい何かが倒れる音にくるりと振り返れば、白の世界で‥‥敵を次々と屠るその姿に目を奪われた。
これは、幻だというのだろうか?
都合のいい夢だと‥‥言うのだろうか?
ふわりと飴色が踊り、下からどこか楽しそうな表情が現れる。
あの時と同じ、
琥珀の澄んだ瞳が、敵を見据えていた。
迷いのない‥‥凛とした眼差しに、
「‥‥‥‥」
ああ、やはり、
彼女なのだと。
「‥‥」
ただの名前を音にして紡ぐ事がどうしてこんなに苦しいのだろうか?
「‥‥‥‥」
名前を呼べば呼ぶほど、心の奥底から閉じこめたはずの想いが溢れ出て、それがひどく胸を締め付ける。
これが夢なのだとしたら、とんでもなく美しく、
そしてとんでもなく残酷だと思った。
「局長!?」
どこですかという味方の声が聞こえる。
慌ただしく雪を蹴立てる音が近くで聞こえたかと思うと、林の間から見慣れた姿が飛び出した。
抜き身の刃を手に、助太刀しますと言わんばかりの彼は、
「‥‥え?」
あちこちに転がる死体の山に目を丸くした。
「‥‥これは‥‥一体‥‥」
いつの間にか戦いは終わっていた。
死屍累々とはまさにこのことだろうか。
島田は点々と転がる死体を一つ一つ目で追い、そうしてようやくその中で一人立ち上がっている人影に気付いて、
「‥‥は?」
今度こそ、言葉を失った。
は、は、と唇から白い息を零した。
少し、息が乱れている。
久しぶりに人を斬ったから、身体が訛っていたのかな?
などと心の中で呟きながら血を払い、刃を収める。
そうして頬に残った血をぐいと袖で拭うと、視線をそちらへと向け‥‥
「‥‥島田さん?」
懐かしい、その声に、島田はびくりと肩を震わせ、やがて、破顔した。
「さん!」
歓喜の声を上げ、駆け寄ってくる。
さながら大きな犬が駆け寄ってくるみたいで、はくすりと笑みを漏らした。
「ご無事、だったんですね‥‥」
島田は良かったと感極まって涙ぐみながら、愛嬌のある笑みを浮かべる。
「島田さんも、無事そうで良かった。」
「自分は大丈夫です!
それよりも、さんこそお怪我は?」
「大丈夫。」
は首を振った。
彼女は本当に一撃も食らってはいなかった。
やはり、強い人だと島田は思った。
「それより、まだ残党が残ってるみたいだから、私は今すぐそっちを片付けに行ってきますね‥‥」
あなたは今すぐに局長と共に本部へと戻って、と彼に指示を出しながらふと注がれる視線に気付いてそちらを振り向く。
ばち、
と視線が一瞬合った。
琥珀の瞳と、紫紺の瞳が一度絡む。
「‥‥っ」
真っ直ぐに逸らすことなく向けられた琥珀に、土方ははっと息を飲んだ。
言わなければいけない言葉があるのに‥‥出てこなかった。
まるで、その言葉を口にすべきではないと言うかのように、喉の奥が張り付いたように。
「‥‥‥」
「‥‥」
お互いに無言で見つめ合う、いや、にらみ合うことしばし。
先に動き出したのはだった。
彼女はすたすたと真剣な面持ちで土方の前にやってきた。
ふわりと香る、柔らかいそれ。
花を思わせる優しい香りは‥‥やはり彼女の、においだ。
僅かに肩を震わせて険しい顔をした彼を、は真っ直ぐに見上げて、言った。
「本日から、大鳥陸軍奉行の補佐に任命されましたと申します。」
「‥‥は‥‥?」
土方は間の抜けた声を上げた。
大鳥陸軍奉行の補佐に任命?
彼女が?
まさに寝耳に水とはこのことで、土方はあまりの事に頭の中がこんがらがってちょっと待てと、彼らしくもなく狼狽
えた声が漏れた。
「‥‥俺は、そんなこと一言も‥‥」
聞いていないと告げる言葉をはさらりと無視して、ぺこりと頭を下げた。
「そういうことで、今日から宜しくお願いいたします。
では早速、残党を片付けて参ります。」
「え、あ、おい!」
まだ混乱する土方を置いて、はひらりと踵を返した。
まるで自由な風のように男の手をすり抜けて‥‥雪の向こうに消えた。
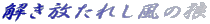
8
 
|