|
ずっとこうしたかったと、
夢に見るほどに願ったのだと、
彼女に言えばどんな顔をするだろうか?
驚くか、
それとも、
照れてしまうか、
いや、きっと、
彼女は笑ってくれる。
笑って、
許してくれるのだ。
こんな浅ましい男の欲も全て、許して、受け入れてくれる。
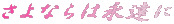
1
夢想するほどに望んだ口付けは、ひどく、甘く、柔らかかった。
触れただけで脳髄までもが蕩けてしまいそうなほどに‥‥柔らかくて‥‥
男は不自然に喉を鳴らしてしまう。
それはまるで初めての口付けに緊張するみたいで、少し決まりが悪い。
「‥‥」
少し離して、顔を覗き込む。
睫をふるりと震わせ、徐々に瞳が開く。
濡れた琥珀が開かれ、ばちりと近しい所で視線が絡むとひどく恥ずかしそうな顔で瞳を伏せてしまった。
目は口ほどにものを言う、とはよく言うけれど、口はやはり何よりも雄弁にものを伝えてくれる。
は知ってしまった。
その唇を伝って、彼がどれほど自分への想いを抱えていたかということを。
ただふれ合っていただけでも十分、分かった。
その口付けが教えてくれた。
まるで、唇の表面から彼の想いが流れ込むかのように。
それほどに強く、激しい感情だったのである。
「?」
「‥‥」
呼びかけに肩がびくんと震える。
怯えたような様子がたまらなく可愛らしい。
大人びているとは言っても色事には慣れていないのだなと思うと‥‥嬉しかった。
「」
もう一度、求めるように呼ぶ。
求められている事に気付いた女はひどく恥ずかしそうな顔であのその、と言い訳を口にしている。
だが面を上げるあたりは拒んでいないのだろう。
「ひじか‥‥んっ」
その、と意味のない言葉を紡ぐ唇をまた、塞ぐ。
今度は先ほどよりも強く。
食むようにすればはびくんっと身体を震わせ、瞳をきつく閉じた。
唇を蠢かせ、感触を楽しむように口づける。
柔らかなそれは男の唇に全てを吸収できてしまえそうだった。
噛みちぎるなどという無粋な事をする必要はない。強く押しつければの唇は溶けてしまいそうだったのだ。
それほどに柔らかく、熱い。
そして、
甘い‥‥
「っ」
不意に、の唇が蠢く。
くすぐったいのか、それとも照れるのか、女の唇が動き男のそれを揺らす。
薄い皮を隔てて柔らかいものが擦れ合わさるのが堪らなく卑猥に感じた。
それはも感じるのか‥‥かぁっと目元が真っ赤に染まり、
「んっン」
怯えたような、だけど、どこか甘さと艶を含んだ声がするりとこぼれ落ちた。
にはそのつもりはなかったのかもしれない。
だが、その声はひどく男の欲をそそる色っぽさを湛えていて、
「っ」
気がつくと土方は頬から手を滑らせ、彼女の後頭部を押さえ込むと隙間無くぴたりと唇を重ねたままぐいと、彼女の
唇をこじ開けていた。
「!?」
驚きに目を見開く。
同じように開いた唇から、何かがぬるりと滑り込んできた。
それは驚くほど熱く、濡れた、男のものであった。
嘘だ‥‥とは思った。
滑り込んだものはの熱い口腔のあちこちを確かめるように撫でながら、やがてはのそれと重なる。
ざらりと肌が粟立つような感触のそれは、
(舌、入って‥‥)
彼の舌だった。
勿論とて、口付けをしたことがないわけでもなく、生娘でもない。
戯れとはいえ沖田と一度肌を合わせた時に彼にも同じように舌を絡ませられて口づけられた。
だが、あの時は相手も状況も違う。
土方は確かにが愛した男で‥‥その男と想いあって口付けを交わしているのだ。
は困惑した。
想い合っているのだから何も怯える事などないのだが、だがにとって土方歳三という男は神聖な男なのである。
彼とて聖人君子というわけではなくどちらかというと派手に遊ぶ男だったというのは知っているけれど、それでも
にとっては高潔な男で‥‥
(こんな、深い、口付けっ)
こんなに深くて、いやらしい口付けをするだなんて思わなかったのだ。
の欲を、ひどく煽るような口付けをするだなんて‥‥
「ん、んぅっ」
ぞろりと舌の裏をなぞられて背筋が震える。
込み上げたのは間違いなく快感というやつで、は思わず漏れた甘ったれた声にぎょっとした。
口付けごときでそんないやらしい気持ちになってしまうなんて、自分がひどく淫らな女になってしまったようで恥ずか
しい。
「ふ、ん――っ」
しかし、己を律するために拳を握りしめれば握りしめる分だけ男の口付けは深くなり、欲は駆り立てられて暴走しそ
うになる。
舌を絡まされ、吸い上げられるたびに漏れる、じゅ、という濡れた音も堪らなく卑猥で‥‥聴覚までも犯されてしま
いそうだ。
いけない。
このまま流されればもっとと恥ずかしく強請ってしまう。
そんな浅ましい女の部分を見られたくなかった。
でも、
でも、
(きもち、いい‥‥)
はとろんと、表情を蕩かせ、押し寄せる緩い快楽の波に徐々に飲まれていった。
「っと‥‥」
どれほどに男に唇を貪られていただろう。
頭がぼうっとしてもう何も考えられなくなり、腰から下がまるで切り離されたかのように感覚が無くなった頃、
の膝がかくんと折れた。
そのまま頽れてしまいそうなのを土方の手が支える。
かと思うと、
「ふぇ?」
突然膝裏に手を差し込まれ、ひょいと軽々と抱き上げられた。
は重力を感じない違和感に顔を上げる。
自分の足がまともに地面を踏みしめていない。
これは一体どういうことだろうか?
まだとろんと力無い表情を浮かべたままぼんやりと視線を巡らせれば、自分を抱えたまま彼は部屋続きになっている
そちらへと向かっているのが分かる。
彼の執務室の奥には扉があって、その向こうにも部屋があった。
扉を開けたその向こうは、
「っ!?」
彼の寝所である。
は身体がぎくりと強ばるのが分かった。
上司、といえど蝦夷にやって来て以来、は彼の寝所に入った事はない。
以前ならばなんとも思わなかったものの、彼に特別な感情を抱いて以来、なんとなく気まずい気がして入る事が出来
なかったのだ。
そして特別、土方が彼女を寝所に招く事もなかった。当然の事だが。
「ひ、土方さん!?」
初めて見る彼の寝所にはの部屋にあるのと同じものが鎮座している。
ベッド‥‥という西洋の寝具であった。
向こうは畳の上ではなくそれの上に寝るのだ。
未だ慣れないとは違い、新しい物好きである土方はやはり柔軟にそれを取り入れ、利用しているらしい。
だからその上にとさりと下ろされた時、は困惑してしまった。
その場所に誘う‥‥その意味を知らないほど、は子供ではないからだ。
「あ、あ、あのっ」
器用に片手で脱がされた革靴が、ことんと床を叩く。
彼も続いて自分の履いていた靴を脱いだ。
それはひどく乱暴に放り捨てるようなのに、の両足はゆっくりと、大切に扱うようにベッドの上に下ろされた。
なんだろう、壊れ物を扱うかのような丁寧さがひどく、胸をざわつかせる。
それを何というのか分からずに戸惑っていると、ぎしりとベッドが軋み、男の身体が覆い被さってきた。
途端感じる自分とは違う温もりとにおいには身体を強張らせ、常に飄々とした彼女らしからぬ狼狽ぶりを見せる。
「あ、わ、私っ」
男の手が女の細腰に手が伸ばされた。
そうしてするりと久遠を鞘ごと奪ってベッドの脇の机に乗せた。同様に自分のも外して、脇差しと刀とを久遠の上
に置く。
まるで身体が重なり合うかのようなそれは何かを暗示している気がした。
それは、一体、なに?
「ひじ、ンっ――」
待って、と告げようとした唇は再び塞がれる。
開いた唇から当たり前のように舌が滑り込んで、吸い上げられ、深く、絡まされる。
それだけでは飽きたらず男は女の身体を押さえ込むように僅かに体重を掛けて逃げ場を奪う。
微かな重みに強ばるに気付き、緊張を解くように優しくの髪を撫でた。
しなやかな指の腹が頭皮を撫でるのがひどく、気持ちいい。
それでなくとも彼の口付けは巧みで‥‥は再びふわふわと心許ない浮遊感に飲まれていった。
の抵抗が、止む。
それを確かめると土方は口付けを止めずに、更に深く、思考を全て奪うように舌を絡めて時に噛んで刺激を送りなが
ら頭皮を愛撫していた手をするりと下へと滑らせた。
その延長上にある白く細い首筋を撫で、浮き出た鎖骨をなぞり、やがては服の上から身体の線をなぞるようになで下
ろす。
サラシと服とに守られた胸は忙しなく上下している。
空気を求めて時折苦しげに漏れる声に気付き、時々唇を離して呼吸の機会を与えてやった。
そしてが我を取り戻す前に再び塞いで何も考えられないようにすると、チョッキの紐を手早く解いた。
勿論、は気付かない。
口付けに没頭している。
翻弄されているの間違いかもしれない。
それを確かめながら全てを解くと今度はその下を守っているシャツと呼ばれる洋服へと手を掛けた。
これは釦で全てが留められており、いちいち外すのが面倒だった。
だが、一つ一つ暴いていく‥‥というのがたまらなく男の征服欲を満たしてくれる。
彼女がいよいよ自分の物になるのだと思えばその焦れったい時間さえもかけがえのないものだと感じた。
ぷつんと最後の一つまで外せば、その下にはサラシが待っており。
角度を変えて口付けを与えながら背に手を回して折り込んだ端を見つけだし、解いた。
これにはやはり、も気付いたらしい。
「‥‥?‥‥ぁっ」
蕩けたような表情から一気に青ざめ、は慌てて土方の手から逃れるように暴れた。
「だ、だめだめっ!!」
口付けで鈍くなった身体をなんとか動かして緩んだサラシを押さえながら身を捩る。
前も後ろも逃げ場はないので結局ごろごろと無駄に回転して彼に背を向ける事で死守した。
「なんで駄目なんだ?」
もう少しという所で抵抗されてしまった土方は不機嫌そうに訊ねてくる。
そうしてこちらを向けと言わんばかりに服を引っ張られ、はだめ、ともう一度強く言った。
「だ、だって‥‥こんなことするなんてっ」
「おかしかねえだろ。」
さもおかしいと言いたげなの言葉の先を攫う。
「俺たちは想い合ってる。互いが互いの事を好いてる。何も問題ねえじゃねえか。」
むしろこうなって当然だ、と言わんばかりの彼の言葉には小さく呻いた。
その通りだ。
無理矢理、ではない。
なし崩し的ではあるが、お互いに好き会っているのだ、何も問題はない。
だが、
「きゅ、急すぎる!」
はその急な展開についていけそうもない。
好き合っているという事さえには十分整理のつかない大事だというのに、この先肌を合わせるなどという所まで
進むなんて。
せめてもっとゆっくりと段階を踏んでいくべきで‥‥
「そりゃ無理だ。」
「ひゃっ!?」
ちゅ、と項に熱く、濡れた感触があった。
彼の唇だと思った次には何とも言えないざらついた感触が項から肩の線までをゆったりを撫でていき、
「ゃ、ぁっ」
ぞわりと肌が粟立つ感触に唇から頼りない声が漏れる。
肌の下でひどい疼きが生まれてそれが身体の中心に集まってくるのが分かった。
「や、やめっ‥‥んっ」
無意識に鼻に掛かった声は、媚びるような響きを湛えている。
彼女が洩らしたとは思えない色っぽく艶めいた声だ。
「んな色っぽい声でやめろとか言われて、やめてやれるわけがねえだろ?」
肩口に歯を立てて男は服を引きずり下ろし、背中を露わにする。
彼女は鬼だから傷は受けない。
だから、白い背中には傷一つ無い。
古い傷も新しい傷も何もなく、まっさらで美しい肌がそこにあった。
誰の痕もつけられていない無垢なそれを見れば踏みにじりたいと思うのが男の心情だ。
「いっ、ぁっ」
薄く、肉のない背中に吸い付き、歯を立てる。
背中の中心に赤が散った。
男の欲を心地よく満たしてくれる。
「ひ、土方さん!ま、待ってくださいってばっ」
「散々煽ったおまえが悪い。」
煽ってない。
は心の中でだけ叫んだ。
声にしなかったのはベッドと身体の隙間に男の手が差し込まれてサラシを解こうとしたからだった。
「や、やだって!」
「俺に抱かれるのが嫌なのか?」
「そ、そういうことじゃなくて‥‥わ、だめ!解いちゃ駄目ですっ!」
「じゃあなんで駄目なんだよ。」
理由を言えよと熱っぽい声が肌の上を滑る。
その声がいつもの余裕をなくしていた。
むき出しの男の欲を丸出しにした声音に、はじんと腰に甘い痺れが走るのが分かる。
惚れた男に心の底から求められている‥‥それが分かればどんな女だって感じるのは当たり前。
だからこそ、怖いとも思うのは女の心情。
心底惚れた相手にだからこそ‥‥臆病になるもの。
「もしかして、怖いか?」
なら安心しろと言う声がひどく楽しげだ。
「痛くはしねえ。‥‥めいっぱい甘やかしてやるぞ。」
甘やかす、という言葉に意味ありげな含みを感じて、はぶんぶんと頭を振った。
「あ、甘やかさなくていいっ!」
「じゃあ、酷くして欲しいのか?」
「ちがっ!そうじゃなくて、こんなことやめ‥‥ひゃっ!」
ぱく、と背後から耳殻に噛みつかれては驚いたような声を上げる。
だがすぐにやわやわと唇で愛撫をされれば甘ったるい嬌声へと変わってしまうのは止まらない。
「や、み、み、やぁっ」
「弱い、か?」
「んっ、ゃだぁ‥‥」
弱い部分への集中的な攻撃に手が疎かになる。
その隙を逃さずに彼女の手の下に己の手を潜らせた。
サラシ越しに感じる、柔らかな膨らみに思わず雄の本性が暴れそうになる。
紳士的‥‥とはいっても、紳士はきっと嫌がる女にこんなことはしないだろうが‥‥あくまで彼女の同意を得てこと
に及びたいと思いその紳士的な思いさえも捨て去って、ただ貪り尽くしたいという気分になった。
「ひ、じかた、さぁ‥‥」
素肌に触れたいと性急な手つきでサラシの隙間を探される。
いやだ、やめて、とは涙ながらに訴えれば、もう一度耳朶をかりと噛まれた。
「は、ぁっ――」
自分でも信じられない甘ったるい声を上げ、喉を晒す。
じんと甘い痺れが走ったと同時に、身体から力が抜けていく。
指先が嫌がるように、まるで、この先を期待するようだった。
もう抵抗できない‥‥そう思ったとき、その耳元で男がこう訊ねてきた。
「俺に、おまえを抱かせてくれねえか?」
ここまで無理矢理しておいて、今更聞くのか、と彼女は心の中で反論した。
反論したけれど声にしなかったのは、彼の声が今までのどれよりも真剣で、切羽詰まったようなものだったから。
まるで‥‥今しか、こうする時間はないのだと焦るような。
確かに、彼が焦る気持ちは分からなくもなかった。
だって、明日にはここは戦場になる。
今度こそ、生きて帰って来られないに違いない、激しい戦になる。
だから‥‥これが最後の機会かもしれない。
彼女を愛する最後の機会に。
そう思えば、彼が焦るのも納得できた。
そして最後の瞬間に、求めてくれるのが自分のことだと思えば‥‥は抵抗などもう、出来るはずもない。
「‥‥?」
は身体から力を抜く。
彼の手を阻んでいたそれも、解いた。
身を委ねる、というより、些か投げやりなそれになってしまったような気がして、無言になった土方には、その
と小さな声で言った。
「‥‥して、ください‥‥」
抱いて欲しかった。
もし、これが最後なのだとしたら、彼の思うままに。
優しくしなくたっていい。
乱暴でもいい。
怖くたって、構わない。
彼が思うままに、望むままに、自分の身体を抱いて欲しかった。
もう既にこの身体も心も、彼のものなのだ。
どう扱おうと、彼の自由なのだ。
そしてそれは投げやりな感情ではなく、自身が望んでいることだ。
抱いて欲しかった。
出来ればきつく。
苦しいくらい。
怖いくらいに。
激しく。
死ぬその瞬間までも、彼の熱や感触が残るほど、
強く抱いて欲しかった。
壊してくれても構わない。
彼に壊されるのならば本望だ。
ただ、それを面と向かって言う勇気はなく、はベッドの白い敷布に思い切り顔を押しつけて甘ったるく懇願する
よりは、初めての情交に戸惑い恥じ入るようにして願った。
一方の土方は‥‥そんな彼女が愛おしくて、堪らなかった。
きっとは彼の表情を目の当たりにしていたら二度と顔を上げられなくなるだろう。
それほどに、土方は極上の笑みを浮かべていた。
彼にそんな無邪気な表情が出来たのかと驚くほどに、邪気のない、嬉しそうな顔を‥‥
「‥‥ああ‥‥」
土方はこくりと喉を鳴らして息を嚥下するとの耳にもう一度唇を寄せた。
吐き出す吐息が熱く、の鼓膜を震わせた。
「安心しろ。」
「っ」
擽る吐息に身体が震え、怯えたようなそれになる。
その肩を手でゆっくりと抱きしめながら彼は言った。
「優しくする。」
そしてその手が再び降り、胸元をまさぐる。
は顔を埋めたまま、もう、暴れない。
ただどきどきとうるさくなる鼓動に拳を握りしめて耐えた。
さっきまでは性急だった手つきは、優しく、穏やかなそれになっていく。
大切にされている‥‥そう思うと恥ずかしくて、嬉しかった。
やがて焦れったいまでの速度でサラシが解かれ、男の手がとうとう、彼女の女たる部分へと触れる‥‥
その瞬間だった。
「土方さん、いらっしゃいますか?」
控えめなノックの音とは裏腹、強い声が扉の外から飛び込んでくる。
無情にも甘い時間を裂いたのは、の抵抗ではなく何も知らない一人の隊士の声であった。
「っ!」
「!?」
二人はばちりと弾かれたように飛び上がり、離れる。
とは言ってもはベッドに齧り付くようなことしか出来ず、離れたのは土方の方であった。
「なんだ!」
身体を起こし、声を返す。
些か尖った声になってしまうのは仕方のない事だ。
それは外にいた隊士も分かったのだろう。
「も、申し訳ありません!伝令がありましたので至急お伝えしようと思ったのですが‥‥」
萎縮してしまった彼の言葉に、ち、と土方は舌を打つ。
彼は悪くない。
悪いのは状況であって、彼に非はなかった。
むしろ、彼の行為は一隊士として当然のことである。なるほど、浮かれていたのは自分と言う事か‥‥
土方は内心で苦笑を漏らし、緩く頭を振って、わかったと応えた。
「支度をしてから行く。ちょっと待っててくれと伝えてくれ。」
「は!分かりました!!」
畏まった声はそれだけを告げ、やがてぱたぱたと足音は遠ざかっていく。
「‥‥」
それを聞きながらくるりと振り返る。
ベッドに張り付いてしまったは微動だにしない。
まるで、自分はいないものと扱ってくれと言わんばかりに、敷布と同化するかのように固まっている。
まあ、無理もないことだろう。
土方とて、彼女にはどういう顔を向ければいいのか、分からないくらいだ。
ただ年上な分、彼の方がその空気を和らげてやる義務がある。
「いつまで張り付いてるつもりだ?」
「うひゃっ!?」
身体を屈めて剥き出しの肩に唇を寄せた。
肌を吸う、というよりは擽るように食むと、は飛び上がった。
よっぽど驚いたか、よっぽどくすぐったかったか、どちらかだろう。
土方はくつくつと笑いを漏らすとそれ以上はせず、離れた。
驚いて振り返ろうとすると、ばさりと身体に彼の外套が被せられた。
「ひ、土方さん!?」
「それ、着てろ。
服、脱がしちまったからな‥‥」
「っ!」
言われては今更のように気付く。
チョッキもシャツも、それからサラシも暴かれているのだ。
胸元を守るものは何もない。
慌てて脱がされたシャツをかき集めて、恥ずかしそうに視線を伏せるその姿が、たまらなく男の欲をそそった。
それは、見なかったことにしておく。
苦笑で脇机に乗せた自身の刀を取ると、まき直したベルトに差し直す。
そうして未だ視線を伏せたままの彼女の頭をぽんぽんと、優しく撫でると、
「悪いな、こんな中途半端になっちまって‥‥」
と小さく謝った。
はいえ、と小さく頭を振った。
彼が謝るべきことではない。
謝るべきは、自分だっただろう。
もっと早く抵抗を止めていれば‥‥もしかしたら彼の望むままに出来たかも知れないのに。
「‥‥おまえは悪くねえよ。」
そう、自分を責める彼女に気付き、土方は苦笑した。
むしろ性急に求めた自分によく応えてくれたな、と思う。
それ以上に、中途半端に期待させ、恥ずかしい思いだけをさせてここに置いていくというのが申し訳なくさえ思った。
「部屋に戻ってろよ。」
土方は着衣を正すと言って、背を向ける。
それがあんまり素っ気ない気がして、は慌ててベッドから飛び降りた。
「こ、ここにいてちゃ駄目ですか?」
怒らせただろうか?
嫌われただろうか?
そんな不安から弱い声になる。
土方はそんな馬鹿な事があるものか、と内心で答え、首を緩く振った。
それは待っていてはいけない、と拒まれた気分になって、は落ち込む。
そんな彼女に、土方は言った。
「次は止めてやれねえぞ。」
「え――?」
彼は肩越しに振り返った。
意地の悪いその瞳には、先ほどの名残だろうか‥‥濡れた色が滲んでいる。
笑みを象る口元が艶っぽくて、はぎくりとした。
「このままここにいるんなら、今度こそ最後まで止まれねえぞ。」
彼は宣言した。
このまま男が戻ってくるまでここに残っていたのならば、先ほどの続きをすると。
そして、今度こそ逃がさないと。
今度こそ最後まで、どんな邪魔が入ろうと最後まで成し遂げると。
つまり、自分を抱く、と言った。
「ぁっ」
先ほどは確かに受け入れたことであったが、改めて言われると羞恥に戸惑う。
その戸惑いや迷いを見た男はくつくつと笑った。
獰猛な色を優しげな色で上塗りして、だけどこれは忘れないでくれと、彼は告げた。
「俺は、惚れた女に何もせずにいられるほど出来た男じゃねえんだよ。」
自分は聖人君子などではない。
ただ一人の、浅ましいまでの欲を彼女に抱いている、哀れな男なのだ‥‥
「う、うそだぁあ‥‥」
一人残されたがそれを認められるようになるのは‥‥もう少し後の事である。

|