|
その人の揺るがない強さに惹かれた。
――その人の子供のような純粋さに惹かれた。
その人の不器用な優しさに惹かれた。
――その人の儚げな生き方に惹かれた。
動乱の渦中にありながら、それでも潔く生きる様は美しく‥‥
――その生き様に、
惹かれた。
その世界にいながら、その人の傍にいると、安らげた。
強くいられた。
優しくいられた。
自分らしくいられたのは、
その人のお陰だった。
その人の強さが好き。
優しさが好き。
それから、
その人の弱さが、
迷いが、
その人の全てが、
――今は、愛しいと思う――
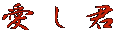
1
慶応四年。
新政府軍と、旧幕府の間で話し合いが持たれ、江戸城を明け渡す事となった。
そうすると新政府軍の動きはますます活発になり、旧幕府軍の人間はたちまち居場所を奪われていった。
幕府の人間は彼らに恭順し、もうじき、江戸は完璧に彼らに明け渡される事だろう。
監視が厳しくなる中、新選組の一同も北へと向かう事になる。
その中、土方はを伴い、江戸に最後まで残っていた。
近藤の助命嘆願のために。
しかし、そろそろ潮時だとは市中の様子を見て、思った。
明日には、江戸を発つべきだ‥‥と。
ぴりぴりと嫌な空気をさせている江戸の市中。
闇の中でもその張りつめた空気は消えず、いや、逆に濃くなっている気がするとは思った。
注意深くあたりへと気を向けながら、は黙って土方の後を追いかけた。
同じく無言の土方の背中は‥‥いつもよりも不機嫌そうだった。
無理もない。
と彼女は思う。
江戸に戻ってからどれだけ、彼は駆けずり回っただろう。
方々に頭を下げ、近藤を助けるための助力を乞うた。
その中には新選組を高く評価してくれた人間もいた。
彼らのおかげで生き延びた人間もいた。
でも、その彼らは掌を返したように、彼を冷たくあしらった。
ひとえに新政府軍を刺激したくないという臆病者の言い訳を口にして。
何度も何度も助命嘆願を願い出たが‥‥その声が届く事はなかった。
何も出来ない歯がゆさに、土方は苛立ちを隠せないようだ。
ぴりぴりと張りつめる江戸の空気は半分彼のせいではないかと‥‥そう思うほど、彼の周りには刺々しい空気がまと
わりついていた。
「、おまえ、先に江戸を出ろ。」
江戸の外れまで来た瞬間、土方はそんな事を言って立ち止まった。
は視線を上げて、それではあなたは?と訊ねた。
彼は、こちらを見もせずに答えた。
「俺は‥‥もう一度近藤さんの助命について直談判してくる。」
そんな言葉にはすいと目を眇めた。
目の前の男が冷静になっていないと分かった。
「‥‥無茶です。」
これ以上は待てない、とは首を振った。
彼と共に行動していたのは、彼が自棄になって無謀な事を起こさないように止めるためだった。
そんな言葉に土方は煩わしげな目をこちらに向けた。
「無茶かどうかやってみなきゃわかんねえだろ。」
「無茶に決まってます。
今、江戸を出るのが遅れたらあなたまで新政府軍に捕まる。」
「そんなの‥‥」
逃げ切ってやると言いたげな言葉に、は無理だと心の中でだけ呟いた。
彼は羅刹ではあるが、その力が発揮されるのは夜だけ。
確かに羅刹はすさまじい戦闘能力を持ってはいるが、それも無限ではない。
それに、敵対する新政府軍は羅刹に対抗する知識を持っているのだ。
そう、銀の弾丸。
それを打ち込まれ、苦しみ喘ぐ沖田や、仲間の姿を見てきただろうに。
土方は夜の街を見つめたまま不機嫌そうに奥歯を噛みしめる。
の正論がひどく煩わしいといった感じだ。
「あなたを待ってる皆を裏切るつもりですか?」
「大丈夫だ。
切り抜ける。」
その自信はどこから来るというのだろう。
はため息を吐いた。
「しっかりしてください。」
彼の焦りは誰よりも分かっていた。
出来るならば彼の思い通りにさせてやりたいという気持ちもある。
でも、ここで彼まで討ち取られてしまっては意味がない。
いや‥‥
彼に死なれたら、は‥‥
考え、思わず目の前が真っ暗になり、は頭を振って暗い考えを振り切った。
それから、努めて冷静で、静かな声で言った。
「今どうするべきなのかは土方さんが誰よりも分かってるはずです。」
そんな落ち着いた声が、土方の感情を逆に、逆撫でた。
「おまえに何が分かる!」
激昂し‥‥思わず、そんな言葉が漏れた。
――何も分からないくせに。
――俺の気持ちなど何も分からないくせに。
そう、言いたげな言葉に、は琥珀の瞳を見開いた。
それからすぐに、
「ぁ‥‥」
その表情が、僅かに歪む。
何かを必死に堪えるようなそれだった。
堪えているのは悲しみだ。
深い‥‥悲しみ。
でもそれを必死に堪えるように、は拳を握りしめた。
それが力を入れすぎて白くなっているのに気付いた。
言ってしまってから、彼は彼女が何も思わないはずがないと気づいた。
だって、彼女も一緒だった。
土方と同じで近藤の事が大好きだった。
彼を親のように慕っていた。
共に行きたかっただろうに、は近藤の願いだから土方についてきた。
断腸の思いで‥‥彼女はここにいるに違いない。
それは分かっていた。
分かっていたけれど‥‥彼女のその冷静な態度に、もしかしたら彼女は何も感じていないのではないかと思ってしま
まったのだ。
有能な副長助勤である彼女は感情を切り捨てるのに慣れていた。
今まで仲間をそうやって切り捨ててきた。
平気な顔をしていたけど、それはただ心を麻痺させ、無理矢理何も感じないようにしていただけ。
本当は‥‥苦しいくせに、悲しいくせに、彼女はそれを押し殺すのが上手なだけだと。
いや、そうじゃない。
表現する事が下手くそなだけ。
それが分かっていた。
何も感じないわけがない。
誰より仲間を、近藤を慕っていた彼女が感じないわけがない。
彼女だって、
苦しいはずなのに。
「‥‥」
土方は拳を握りしめ、地面を睨み付けた。
子供じみた八つ当たりだ。
彼女は何も悪くない。
彼女はいつだって自分の事を、近藤の事を、新選組の事を考えてくれている。
多分正しいのだ。の言う事は。
それは頭の片隅で分かっている。
「っ」
土方は苛立ちに奥歯を噛みしめた。
ぎり、と嫌な音が聞こえた。
いっそ、詰ってくれればいい。
泣いて、喚いて、
酷いと叫んでくれればいい。
そうして、責め立ててくれればいい。
今の事も。
それから‥‥近藤の事も。
「あなたのせいだ」と。
罰してくれればいいのに。
でも、
「土方さん‥‥今まで新選組のために命をかけた人たちが、何を思っていたか‥‥分かりますよね?」
彼女はどこまでも優しかった。
あなたこそ何も知らないくせにと彼を詰る事も、勝手にしろと突き放す事もせず、
彼女はただ静かな声で、彼の荒んだ気持ちを落ち着かせるみたいに言った。
「源さんが‥‥死んでいった隊士たちが‥‥
何を思って、戦ってきたか。」
分かりますよね?
と彼女は言う。
「彼らは、新選組を愛し‥‥そして、あなたを愛した。」
凛と強く、揺るぎないその生き様に、誰もが惚れた。
彼と共に歩みたいと誰もが願い、彼が見せてくれる夢を信じて戦って、
そして、散った。
自分が信じた男についていって‥‥命を落とした。
そんな彼らが、
「今の土方さんを見たら‥‥悲しみますよ。」
咎める、というよりは、優しく諭すような声だった。
その言葉が、
土方の胸にすとんと落ちてきた。
「悲しむ、か。」
不意に彼は遠い目をして、肩の力を少しだけ抜いた。
その瞬間、彼を纏っていた刺々しい空気が消えた。
彼は遠い目をしたまま、なあ、とを呼ぶ。
「残された奴は、先に逝った奴らの意志も継ぐべきだと思うか?」
彼は、散っていった者達の意志を、希望を、継いで生きるべきかと。
「はい。」
静かな問いに、は迷わず答えた。
その瞬間、井上の優しい声が聞こえた気がした。
『彼を頼む』
そんな声が。
「ったく、だったら俺が死ぬまで荷物は増えるばかりじゃねえか‥‥」
の答えに、土方は苦笑を漏らした。
確かに、彼は生き続ける限り彼らの想いを背負い続ける事になる。
それは彼にとって重荷となることだろう。
彼らの想いが、彼を追いつめる事になるだろう。
でも‥‥とは心の中で呟く。
「――私も背負います。」
彼が背負ったその重荷の半分を。
彼に託された沢山の想いを。
これからも増え続ける想いを。
彼と共にある限り、背負い続けると。
それが罪だろうがなんだろうが、も共に背負う。
彼が押しつぶされないように。
彼が一人で苦しむ事がないように。
「‥‥」
真っ直ぐこちらを見つめるの瞳に、土方は一瞬、口を噤む。
そして僅かに顔を顰め、何かを言いたげな顔になるが、頭を振って、代わりの言葉を口にした。
「状況が新選組に不利になればなるほど、俺は冷静になるべきなんだろうな。」
いつもと同じ声でそう呟き、視線を江戸の中心から外れへと向ける。
「大将が戻ってきた時、居場所がなくなってたんじゃ笑い話にもなりゃしねえしな。」
ぽろっと出てきた軽口に、はそうですねと言って笑った。
「‥‥行くぞ。」
やがて土方は短く言って、走り出した。
は黙ってその後ろを続く。
仲間との合流地点へと、ただひたすらに走った。
「お疲れさまです。」
夜の道を駆け抜け、山間の、合流地点へと到着すれば、島田がほっとしたような顔で出迎えてくれた。
「江戸の様子はどうでしたか?」
問われ、は首を緩く振る。
「もう、あちこちぎすぎすして‥‥いつ新政府軍が動き出すか分かったもんじゃないよ。」
「そうですか‥‥」
言葉に島田は表情を曇らせた。
そしてすぐにそれを引き締めると、
「では、すぐに出発できるように皆に伝令してきます。」
といって走り出そうとする。
お願いと言いかけたの言葉を、土方が待てと遮った。
そして、彼は驚くべき言葉を口にした。
「悪いが島田。
と一緒に先に北に向かってくれ。」
「土方さん?」
どういう事ですか?とは彼を睨み付ける。
まだ分かっていないんですかと言いたげな彼女に、土方は冷静な眼差しで答えた。
「俺は助命嘆願を続ける。」
その言葉が単なる感情からではない、というのはその冷静な声音から察せられた。
冷静に考えた結果、出た言葉なのだと。
でも、
「危険です‥‥」
それは明白だった。
「これは副長命令だ。
俺もすぐに後を追うから、もうしばらく待ってろ。」
しかし、土方は頑として譲らない。
そればかりか、副長命令とまで言われ、も島田も承伏せざるを得ない。
上の命令は絶対、なのである。
「‥‥」
島田は不服を飲み込むように沈黙した。
やがて、
「わかりました、副長。」
こくりと頷く。
それを確かめると今度はの方へと視線を向けた。
――共に背負うと言ったのに。
は咎めるような瞳を彼に向けた。
その瞳に込められている想いを、土方は気付かないわけがない。
でも、反論は許さないという強い意志の瞳で、彼はこちらを見つめていて、
「‥‥分かりました。」
は静かに頷くしかなかった。
そして彼はまた来た道を戻り始める。
ひとりでたくさんの荷物を背負い込もうとするところが、彼の生き方なのかもしれない。
誰かと共に、痛みを分かち合うなんて、彼には出来ないのかもしれないと。
それはひどく悲しく、寂しい事だと。
闇に紛れて消えていくその背中を見て、は不意に不安に駆られた。
大きな、その背中が、
ただがむしゃらに、死に急いでいるように見えて、
「‥‥無事で、戻ってきて。」
思わず、そんな願いが口からもれた。

|