|
はら
はら
空から雪がこぼれ落ちてくる
はら
はら
受け止めようと開いた手のひらをすり抜けていく
優しいものが
愛しいものが
こぼれ落ちて
儚く、消える
手を伸ばしても
掌を握りしめても
こぼれ落ちる
崩れ落ちる
はら
はら
残ったのは
空っぽの器
空から、雪は降り続ける
空っぽの私を冷たく白いもので満たすように
或いは、
塗り潰して消してしまうように
何もない、何も持たない私は
存在する意味などない
世界から、全てが消えた
私を作り出す全てが、
白で塗り潰され、
消えた
私にはもう何も、ない
何一つ、残らない
「おいで――」
後は静かに瞼を閉じれば、穏やかな死が訪れる。
きっと誰も気付かない。一面は真っ白く塗り潰されているのだ。色を持たない自分に誰も気付くはずもない。
それは悲しい事なのか嬉しい事なのか、もう分からないしどうだって良い。
ただ世界はとても静かで、冷たいものだった。
そうどこかで諦めて瞳を閉ざし、永久にこの世界に別れを告げようとしたその時だった。
「おいで」
手が、差し伸べられた。
その人は、酷く綺麗な瞳を向けていた。
この汚れきった世界にまだ、こんなに綺麗なものがあったのかと驚く程。
純粋な目をしていた。
「何も怖い事などない」
そう言って、彼は、
冷たい心を、
身体を、
そっと抱き上げた。
大きくて、優しい手。
触れられた所から、
優しさが、
ぬくもりが、
滑り込んでくる。
空っぽの中身を、それでめいっぱい満たすみたいに。
「名は何という?」
優しい声でその人は問いかけた。
ぼんやりと見つめていると、彼はそうか、と一人で何かを納得したような顔で頷く。
ふわり、ふわりとこぼれ落ちる雪が、その人の頭に積もるのをじっと見つめていた。
それからその人は、そうだ、とまた一人で声を上げ、
「今日から――おまえの名は『』だ。」
。
と呼んで、その人はぎゅっと抱きしめてくれた。
全てを失った。
降りしきる雪の中。
全てが白く染め上げられた世界の中で、全てを。
優しいものも。
愛おしいものも。
全部。
でも、その代わりに、
――泣きたくなるほどの温もりと、
新しい名を手に入れた。
――という名前だった。
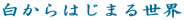
1
文久二年――
世は、幕末。
長きに渡る江戸という安泰の時代にも、少しずつ暗い影が落ち始めていた。
それは今という平穏に飽きた人々が変化を求めるが故か。それとも光の裏には必ず闇がある故か。
少しずつ、密やかに。
しかし、確かに。
闇は広がっていく。
誰にも抗う事など出来ない。許されない。
逃れる事も出来ない。
一度回り出した歯車は止まらない。いずれ世界を大きく動かして、壊れてしまうまで。
闇は少しずつ拡がっていく。
穏やかに見えるこの、京の町にも。
水が、静かに大地に染みこんでいくように。
ひっそりと、確実に。
いずれ大地からにじみ出るまで、誰も気付かない。
しかしその闇は、
まだ――そこには届かない。
風に吹かれて花弁が舞い落ちた。
穏やかな風はゆるゆると、それを彼の元へと運んでいく。誘うようにはらはらと、彼の手元に。
しかし、どれほどに楽しく舞ってみせても彼は顔も上げない。ただ無言でさらさらと筆を滑らせていき、時折止まっては空を見上げて思案し、やがて再び筆を動かす。
春風はつまらないと言う風に男の長い黒髪を揺らして、部屋を通り抜けていった。
不意に、
ばたばたとあわただしい足音が聞こえ、男は眉間に皺を刻む。不機嫌そうな皺は役者のように美しく整った美貌を台無しにさせているが、今では彼――土方歳三の癖の一つになってしまっている。
不快げに眉を寄せて顔を上げれば、遠くからやけに騒がしい音が聞こえた。
一体何事かとその理由を探るより前に、
「またあの二人が戦ってるらしいぞ――」
若い隊士の声が飛び込んできた。
足音の主かどうかは分からない。否、誰が発したものかなどはどうでも良い。
そんなことよりも、
『あの二人』
その言葉が男の表情を更に険しくさせるのだ。
「またか」
呻くように呟く。
ここの所おとなしくしていたと思ったから油断をしていた。そういえば今日は二人とも非番だっただろうか。暇を持て余した二人が向かう場所なんて限られているし、そこでばったり顔を合わせたらどうなるかも分かっていたのに。
くそ、と吐き捨てて腰を上げようとしたところで、ふすまの向こうから声が掛かる。
「土方さん――」
「斎藤か」
静かな声で三番組組長――斎藤 一は答え、ふすまを開けた。
常のように漆黒の衣に身を包んだ男は、やはりいつものように無表情で言い放った。
「総司とが……」
予想通りの二つの名に、土方は頭痛がしてきそうだ。
「一番組の沖田組長と、副長助勤が手合わせしてるって?」
隊士達は口々に言いながら廊下を走った。
彼らが目指す先――道場は溢れんばかりの人でごった返している。
まるで珍しい見せ物にでも群がるかのように、集まった隊士たちはひょこひょこと開けはなった戸口より顔を出して中を覗き込んでいた。
その真ん中には二人の人間の姿。
「今日こそ一本取らせてもらうからね」
にこりと、どこか悪戯っぽい笑みを湛えて一番組組長――沖田総司は告げた。
「すました顔してられるのも今の内だけだからな」
対する副長助勤――は、口元ににやりと挑発的な笑みを浮かべている。
互いの手には木刀。
互いの顔には笑み。
しかし、
ぴりりと痛い程に張りつめた空気が互いの間に存在していた。
それぞれが殺気を放ちながら互いを見つめたまま、口元に笑みを浮かべているのだ。
「まだ、始まってなかったか?」
「ああ、まだだ」
隊士達がお世辞にも小声とは言えない声で囁いているのは、もう二人には聞こえない。
彼が勝負を持ちかけ、それにが応えた時から互いに相手の事しか聞こえていないし、見えてもいない。
「ねえ、。賭をしない?」
「総司が賭なんて珍しい。博打は嫌いだって言ってなかった?」
「まあね、あまり好きじゃないけど、面白いかなって」
「いいよ、何を賭ける?」
が問い返せば、木刀を構えた沖田の目がにいっと細められた。
それは酷く妖艶な笑みだ。
漂う色香に知らぬ人間ならばころりと騙されてしまうだろう。しかし、甘い睦言を吐くような目ではない。その瞳の奥には凶暴な色を湛えている。
まるで、獲物を前にした獣のように。
貪欲に、凶悪に、相手をどう食ってやろうかと考えている目。
「負けた方が、勝った方の言うことを何でも言うことを聞く……っていうのはどうかな?」
へぇ。
も同じく目を細めた。
作られた人形のように整った顔立ちが、美しい微笑を浮かべている。だがはやり、その瞳の奥にも明らかに凶暴で冷徹な色を浮かべていた。
食えるものならば食ってみろ。逆にこちらが食い殺してやる。
そう言わんばかりの目で睨め付けるもまた、沖田と同じ質の人間なのだ。
「いいね。のった」
は楽しげに答えた。
「おまえを地べたに這い蹲らせてやるよ」
そうして、嘲笑うように言えば、
「僕も、が地面に這い蹲る姿が見てみたいな」
沖田は笑みを深くする。
――カン。
と木刀の先が床を一度叩く。
それはの癖。
そして、それは、
「――行くよ!」
戦いの合図。
音もなく互いに床を蹴れば、後に残るのはの髪、飴色の軌跡。
――カンっ!
一合。
互いの木刀が小気味の良い音を立てて合わさった。
おお――
歓声が辺りから上がった。
その雑音も二人の耳には届かない。
合わせたまま、ぎりぎり、と近い距離でにらみ合っている。
「今日も相変わらず綺麗な顔してるね、」
かち合わせたまま沖田の口から出るのは、緊迫感のない言葉だ。
「それはありがとう。でもその言葉の後に「だから傷つけたくなる」とか言われそうなんだけど?」
それに返すも緊迫感のない常と変わらぬ声。
まさか、と沖田が笑った。笑った瞬間に、力が入りぎりりと嫌な音を立てて木刀が軋んだ。
「それは考えすぎだよ。僕は思った事を言っただけ」
「へえ、本当に?」
「折角褒めてあげたんだから喜んだら良いのに」
「うわー、うれしいなー」
「酷いな。馬鹿にするなら、」
すいと互いの瞳を細め、力で鬩ぎ合うように木刀を押し付け合い、
「本気で斬っちゃうよ――」
カン!
どちらともなく、その反動で後ろへと大きく飛んで離れる。
着地と同時にふわと互いの着物の袖が揺れた。
「はっ!」
続けざまに、沖田が目測するのさえ危うい突きを繰り出してくる。
それをは体勢を低くして避け、そのまま身体を伸ばす勢いを乗せて下から掬い上げるように木刀を振るった。
常人であれば顎を砕かれている一撃を沖田は危なげなく身体を反らし、とん、と床を蹴って距離を取る。
そしてすぐに、
「――」
ひゅ、と風のように走った。
「いつ見ても、沖田さんとさんの手合わせはすごいよなぁ」
見守っていた隊士の一人が呟いた。
誰かがそうだなと答えた気がする。今更という風に笑った人もいた。
その誰もが魅入られたように二人の戦いを見つめている。
彼らの戦い方は、美しく、鮮やかで、見事だった。
繰り出される一撃も。
流れるような動きも。
風のように走る姿も。
すべてが強く、早く、時に柔らかく。
人の目を惹き付けて離さない。
呼吸さえも忘れてしまいそうな程、瞬きすら惜しいと思わせる程、見事な戦い。
綺麗と、誰かが言った。
荒々しいと、誰かが言った。
「いいぞー、総司やれやれ!」
だが見惚れる隊士とは違い、囃し立てる人物もいる。
それは幹部の一人。まだ幼い顔立ちだが、八番組組長――藤堂平助だ。
「! 総司なんかに負けるなよー」
その隣でもう一人の幹部が声を上げた。
二番組組長――永倉新八の大きな声が道場に響く。
合わせる度に、二人の笑みは深くなる。
それは酷く楽しげで、まるで子供のように無邪気な笑みだ。
実際彼らは楽しくて仕方がなかった。なんせこれほどに強い相手と打ち合えるのだ。楽しくないわけがない。
でも、やはりそれでは彼らには物足りない。
「ねえ、……やっぱり木刀なんかじゃやった気分にならないよね」
唐突に言って、沖田が木刀を投げ捨てた。
決着の付かない戦いに飽いたわけではない。
その目は未だ、爛々と輝いている。最初に打ち合った時よりもずっと凶暴に。
「そうだな。やっぱこんな偽物じゃやった気分にならないね」
もそう答えて、その手から木刀を放った。
そして二人は同時に床を蹴って、後ろに飛んだ。
「お、おいやばいぞ!」
ぎょっとしたのは、傍観を決め込んでいた十番組組長――原田左之助である。
まずい。
二人が走った先にあるのは、木刀じゃない。
偽物の刀ではなく、
二人同時にそれの柄に手を伸ばす。
同時に、すらりと一気に鞘から刀身を抜き放つ。
互いの手にあるのは銀色に煌めく、重たい刀。
それは本当に人を殺す武器。
「行くよ」
「掛かってきな」
抜き身の刃を携えた二人の身体から、先程よりもずっと濃密な殺気が迸り、部屋の中の空気が重苦しいそれで膨らみ爆発、
「――てめえら、いい加減にしろ!」
まるで空気が弾けたかと思わせるような、怒号が轟いた。
開けはなった戸口に現れたのは、思い切り不機嫌顔の土方の姿。
その姿を見るや否や、外野は蜘蛛の子を散らすように逃げていくのであった。
ここは――壬生屯所。
そこに住まうは、壬生狼と呼ばれるならず者。
別の名を――新選組――
誰かが、彼らを人斬り新選組と呼んだ。
随分と血腥い名前を戴いたものだと、新選組の面々は豪快にも笑い飛ばしたものである。
闇は静かに拡がっている。
けれどもその場所に、影は、まだ、届かない。
次 頁
|