|
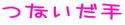
新選組の鬼副長――土方歳三は、たいそう男前だ。
繊細な顔立ちは、役者を思わせるほどに。
そんな彼は、たいそう女に人気がある。
ちょいと外を出歩けば、袖にいつの間にか文が差し込まれ、
島原に行けば大抵の女は土方に群がる。
共にいる男連中はなんとも面白くないものだと思った。
しかし、女に人気があるというのは、いいことばかりではない。
女というのは厄介なもので。
綺麗な女ほど、自尊心が高い。
気位の高い女というのは、より高みを目指して、より相応しい男を隣に並べたがるものだ。
そして、
何より己が愛されているのだと、確かめたがる。
何より自分が愛されているのだと、知らしめたがる。
女とは鬱陶しいもの――
「だーかーら、いい加減にしてくれよ、土方さん。」
ほとほと困り果てた、という風に藤堂が呟く。
言われた土方は沈痛な面もちだ。
いい加減にしろ。
と言われても、彼に否はない‥‥はずだ。
「今日も来てるんだってばー」
「わかってる。」
屯所の入り口がやかましい。
そして、さっきから隊士たちが浮ついているのも知っていた。
また、
来た‥‥
土方は鬱陶しげに髪をがりがりと掻いた。
「今日こそは、土方さんとお話しするまで帰りませんって、玄関に座りこんじまったんだぜ。」
面倒な。
口の中で呟くと、藤堂は半眼になって、告げた。
「蘭菊さんの事は、土方さんがなんとかしてくれよ。」
突き放すような言葉だった。
蘭菊。
という花魁と出会ったのは、二月ほど前。
いつものように島原に行って、酒を飲んだとき、初めて出会った。
それはそれはたいそう綺麗な花魁で‥‥幹部達は一斉に心を奪われた。
がしかし、これもいつものことだが、蘭菊が気に入ったのは土方で‥‥
彼女はべったりと彼に寄り添うようにお酌をし続けた。
綺麗な女に言い寄られて気分の悪い男はいない。
仏頂面が少し緩む、なんぞという瞬間まで見せたのだ、これはもう蘭菊にとっては、落ちた‥‥と思った
だろう。
しかし、
一夜の関係さえ結ぶこともなく、彼は早々に一人帰ってしまい、なおかつ、それからぱたりと一度も来な
くなった。
自他共に認める美しい女。
蘭菊は、その矜持をずたずたに切り刻まれた気分だ。
一夜の関係さえなく。
まるで興味もないというように文一つ寄越さない。
今まで彼女が甘く微笑めば、落ちなかった男などいない、というのに。
これはいかなる事か。
蘭菊は、それから頻繁に新選組の屯所にやってくる。
屯所に来れば、大抵の隊士・幹部は鼻の下を伸ばす。
やはり、自分は美しい。
いかな鬼副長と言われようと自分に落ちないはずはない。
しかしやはり、
土方は文を寄越さない。
顔も出さない。
それからやってくる頻度は高くなった。
五日おき、二日おき、毎日。
確かに男ばかりの屯所に、麗しい女がくれば華やぐ。
でも、だ。
毎日来られては非常に迷惑だ。
しかも、
毎日のようにくる彼女をあしらうのは藤堂や、永倉だ。
申し訳ないと謝るたびに、彼女の表情が冷たいものになっていく。
「また、あんたか」
と言いたげなそれだ。
「オレ、もう嫌だって‥‥」
藤堂はげんなりとした顔で言った。
土方とて同じだ。
面倒だ。
「土方さんがあんまり顔出さないもんだから、心に決めた人でもいるんじゃないのかって疑ってるみたいな
んだって。」
もうそれでいい。
そう言うことにして諦めて欲しい。
「でも、それならなおさらその人間がどんなだか見たいってさー」
自分よりも不細工な女なら自分が取って代われるとでも思っているのだろうか。
がやがやと、玄関口は騒がしい。
ばたばたと慌ただしく走る足音が響いた。
それとは逆に、どすどすと不機嫌そうな足音。
永倉だろうか。
彼も文句を言いに来たのだろう。
今日こそ限界か‥‥
はぁ。
と一つため息をついて、彼は重い腰を持ち上げた。
「平助。」
「なんですかー?」
呼びかけに疲れた返事。
そして、同じように疲れた声で土方は言う。
「おまえ、ちょっくら女物の着物着て出てこい。
こいつが俺の心に決めた女だって言ってやる。」
「嫌だっての!」
広々としたはずのそこには、年若い隊士の姿が勢揃い。
揃いも揃って鼻の下を伸ばし、そこに座るただ一人の女性を見ている。
「あら。」
足音に気付いて、蘭菊は顔を上げた。
それから華も綻ぶような美しい、極上の笑みを湛える。
「土方さん。」
心底嬉しそうに自分を呼ぶ声は、甘い。
普通の男なら、いちころ‥‥と彼女も自負している笑みだ。
しかし、土方は困ったような顔でそこに立っていた。
興味津々、といった隊士達の眼差しに土方が「散れ」と凄みをにじませて言う。
彼らはやや残念そうな顔で互いを見遣り‥‥それから、ゆっくりとその場所から人が遠ざかっていった。
「お会いしたかったです。
顔も見せてくれないなんて、つれないお方。」
咎めるような、拗ねた言葉を零しながら、彼女はゆっくりと近づいてくる。
甘いにおいがする。
彼女が焚きしめている香だろうか。
やけに鼻につく、と思った。
「悪いが‥‥もう、ここには来ないでくれねえか。」
唐突な言葉に、蘭菊は目を見張る。
「どうして、です?」
どうしても何も‥‥と土方は思う。
「私はこんなにお慕いしておりますのに。」
別に何を言ったわけでもないというのに、何を誤解しているというのか。
土方は疲れたようにため息を零す。
その態度に、蘭菊は更に声を尖らせた。
「やっぱり、土方さん‥‥心に決めた女性がいらっしゃるんですね!」
なんてわめき立てる。
金切り声をあげながら。
喧しい。
と思う。
この屯所にも二人女がいる。
でも、彼女たちはそんな声を上げない。
特に一人は‥‥
女らしさの欠片もない。
そういえば女だったか?
と時折思い出すくらいだ‥‥と言えば、彼女は怒るだろうか。
「土方さん!」
返答のない土方に、じれたように蘭菊が声を上げる。
だから、
その声を止めろ。
「うるせえんだよ。」
その口から、低い獣のうなり声のようなそれが漏れる。
それを、
遮るように――
「土方さん。」
凛とした声が耳を打った。
聞き慣れた声。
助け船を出してくれるであろう‥‥その人の声に、土方は振り返る。
そして、振り返って、
「――」
そこに立っていた人の姿を認めて、目を丸くした。
鮮烈に目に飛び込んでくる。
鮮やかな菖蒲色の着物を着たその人の姿。
白い、透き通る肌。
目元の青が、切れ長の瞳を美しく彩り、
つややかな赤い口元を綻ばせる、
まるで人形のように美しい顔立ちをした、
女の姿――
「こちらにおいでだったのですね。」
凛としたよく通る声で言って、こちらに近づいてくる所作は優雅である。
「お探ししました。」
こちらを見上げる琥珀の瞳は足しかに見覚えのあるもの。
でも、自分を見るその目はいつものそれより随分と柔らかく、そして色っぽい。
言葉さえ失うほどの、絶世の美女。
それが目の前にいた。
土方は勿論、蘭菊も目と口とを開けて魅入っていた。
「あら?」
しゃら。
と飴色のまとめられた髪に挿した簪が涼やかに音を立てる。
蘭菊の方を見遣って、
にこり、
と鮮やかに笑った。
その瞬間、蘭菊は我に返る。
我に返ると同時に、目の前の女性が、
『土方の心に決めた女』
なのではないかと思いこむ。
そして、同時に、
「‥‥」
その顔を、じっと‥‥見つめて‥‥
「?」
――負けた。
蘭菊は、がくりと肩を落とした。
目の前の女はどう逆立ちしても勝てそうにもないものを持っていた。
喚く気も起きず、
「し、失礼いたします。」
蘭菊は疲れた声で、とぼとぼ、と屯所を出ていくのだった。
それを玄関口に残された二人は、見送り‥‥
「‥‥ったく。」
姿が完璧に見えなくなるや否や、その口から聞き慣れた乱暴な言葉。
睨み付けるような瞳で彼女は振り返ると、
「何やってんですか、土方さん。」
女一人も追い払うことが出来ないんですか?
と呆れた声で言った。
それはいつもの彼女のものに戻っていて、
「‥‥」
土方はほっとため息を漏らす。
それからくしゃりと顔を歪めると、
「上手く化けたもんだな‥‥」
と零す。
見事に化けたものだ。
そりゃもう、度肝を抜かれるくらいの化けようだ。
「一に感謝してくださいよ。」
「斎藤?」
「そうですよ。
あいつが、助けてやってくれって言いに来たんですよ。」
だから、
とは言った。
どうやら、斎藤の機転のおかげらしい。
土方は苦笑をした。
「ああ、斎藤には後で礼を言っておく。」
「そうしてください。」
「おまえも‥‥悪かったな。」
「いーえ。」
は答えて、ふと、土方の視線に気付く。
彼はじっとこちらを興味津々といった風に見ていた。
上から下まで。
「‥‥‥な、なんですか。」
怪訝そうに眉を寄せる。
土方は顎に手を当てて、ふむ、と一つ呟くと、
「おまえ‥‥やっぱり綺麗な女だな。」
臆面もなく言ってのけた。
は?
とはあんぐり口を開く。
その顔はちょっと間抜けに見えるが、は綺麗な女だと思う。
常に横にいる時から顔が綺麗なのは知っていた。
ただ、男の装いをしていた事もあって‥‥そう気付かなかった。
着物を着て、化粧をすれば、その美しさを改めて気付かされるのだ。
女としての、
美しさを。
「‥‥お世辞言っても、何も出ないですよ。」
じーっと見つめられることに居心地が悪くなったらしい。
は言って、そのまま屯所の中に引き返そうとする。
それを、
――ぱし――
「え?」
手首を掴んで止める。
なに?
とは顔だけを振り返った。
「、これから出掛けるぞ。」
唐突に土方が言う。
は「はぁ?」とまた口を開けた。
出掛ける?
出掛けるって‥‥
「ちょ、わ!?」
土方は腕を掴んだまま歩き出した。
そんなもんだから、は僅かに体勢を崩しながら彼の腕に縋り付く。
「ちょ、出掛けるって‥‥今から?」
「ああそうだ。」
「この格好で?」
「折角そんな綺麗な形してんだ‥‥見せびらかしておけ。」
「何言ってんですか!」
本気で出掛ける気らしい。
「甘味ぐらいなら馳走してやるぞ。」
そう言って振り返った彼は、酷く嬉しそうな顔をしていて‥‥
なんで。
そんな嬉しそうなんですか。
と聞いてやりたかったけど、なんだかこっちが恥ずかしくなる答えが返ってきそうで、
「‥‥女が全員、甘味が好きだと思わないでくださいよ。」
は唇を尖らせて、可愛くないことを言ってみせた。
その言葉に彼は意地悪く笑う。
「いらねえのか?」
「折角だから、奢ってもらいますよ。
とびきり高いやつ。」
「ああ、遠慮するな。」
誰がするもんか。
そう思いながら、はしっかりと捕まれた手を引き離した。
それから、
「‥‥今日だけですよ。」
その手に己の手を絡ませる。
驚きに見開かれた目は、やがて、
「‥‥ああ。」
酷く愛おしいものを見る目へと変わった。
春の優しい日差しの下。
つないだ手は酷く、暖かくて‥‥
離したくない――そう、お互いに思った。
土方さんがいかにもてるか書きたかったんです(笑)
|