|
その光景を見た瞬間、土方の眉間は思い切り深い皺が寄った。
「なにしてんだ、おまえ。」
意識するではない低く、怪訝そうな声が口から漏れ、問いかけには振り返る。
「あ、土方さん。」
お疲れさまです。
と言うそれはいつもの彼女だ。
だけど、だけど‥‥
彼女がしようとしているのは、いつもの彼女らしく無いというか、それ以前に普通の人
らしくないというか‥‥
「てめえで首を落とすつもりか?」
その光景にそれしか答えが浮かばずに呟く。
と、は笑った。
「違いますよ。」
じゃあなんだ。
それ以外にその行動に答えがあるのか。
の手には小刀。
そして、それを、首の後ろに当てている。
そのまま一気に首でも落とすつもりとしか考えられない。
小刀じゃ、一気には斬れないだろう‥‥
っていうか、あれじゃ苦しいだろうな。
そんな事を考えたあたり、彼は少なからず衝撃を受けているのかもしれない。
しかし、彼女は言う。
「髪を切ろうかと思って。」
「‥‥‥」
一瞬、土方は言葉を失う。
眉間に皺を刻んだまま、数拍‥‥黙って‥‥
「おまえに普通ってもんを望んだ俺が馬鹿だったな。」
一人呟いた。
「え?なに?」
聞こえなかったらしい、は首を傾げた。
それに答えず彼はどすどすと床を踏みならして部屋に上がり込む。
むすっとした顔で彼女の前に回ると、どさっと腰を下ろした。
「小刀で髪を切る馬鹿がどこにいるんだ。」
おまえは本当に女か?
と言われては「だって」と唇を尖らせた。
「邪魔だったんですよ。」
かなり論点のずれた返答に、土方はもう一度ため息を零した。
邪魔と言われた髪をちらっと見る。
随分と長くなったそれは、の腰ほどまで伸びていた。
「切っちまうのか?」
「だって、邪魔でしょ?」
これ。
とは髪に手を伸ばす。
それよりも先に、土方の伸びた手がその一房をつかんだ。
滑らかな手触りの。
綺麗な飴色をしたそれ。
指の間からさらさらとこぼれ落ちる様は、光の加減でまるで砂金のようにも見えた。
「土方さん?」
「切るな。」
「え?」
唐突に言葉を告げられた。
切るな。
という言葉。
はまん丸く目を見開いていた。
どうして。
と問いかけるように。
土方は目を眇めて、さらさらと流れる髪を見つめて、
「俺は、これでいいと思う――」
ただそれだけを呟いた。
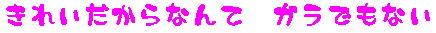
土方さんは素直に褒めない
|