|
「へーすけ、トリックオアトリート!」
「誰が平助だ!先生つけろ先生!!」
「いいから、悪戯させなよ。」
「普通はお菓子だろ!!」
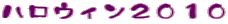
我が校には、藤堂平助というそれはそれは可愛らしい先生がいる。
担当教科は体育。
教師‥‥とは言われていても、なんていうか、友達、みたいに気安い存在なので、皆そいつのことを「平助」とか「へー
ちゃん」とか呼ぶことが多い。
そういう時は決まって「先生をつけろ」って怒るんだけど、それがまた楽しいから生徒は笑いながら呼び捨てにするんだ。
私もその、一人。
「仕方ないじゃん。
先生っていうよりもへーすけって感じなんだもん。」
私が不満げに言うと、仕方なくねえよ、と平助は反論した。
「分かってんのか!?
オレ、年上!教師!!」
「‥‥でも、私よりちっこいと。」
「うっせー!!」
めっちゃ気にしてる所を指摘すると、平助は顔を真っ赤にして怒鳴った。
「お、オレはまだ成長途中なの!」
「へぇ、24にして成長途中‥‥どんだけ足掻くつもりで?」
「ううううううるせぇな!」
「いいじゃん、別に、ちっこくて可愛いのに。」
「かっ‥‥」
可愛いという言葉は男子的にはNGだというのを知っている。
でも、あえて使うのは、私が若干Sッ気があるからかもしれない‥‥平助限定で。
平助はわなわなと震え、あまりの怒りとショックの為か、口を動かすけれど言葉にならず、結局「ば」という音だけで終
わって、しゅうと鎮火。
撃沈?
「‥‥‥」
拗ねたように背中を向ける彼に、私はくすくすと笑みを漏らして、ごめんごめんとその丸まった背中を叩いた。
先生に対して気安すぎるかもしれない。
「暗い顔しないでさー
今日は楽しいハロウィンですよー?」
「‥‥誰のせいだと‥‥」
平助はちろっと私を睨んで、この時になって漸く、私の格好に気付いたらしい。
ぎょっとしたように目を見開いて「おま」と言って言葉に詰まった。
「おまけ?」
連想して単語を上げてみた。だけど、意味が全く分からない。他に色々浮かんだけど、それが一番女子的にセーフだった。
「お、おまえ、なんて格好!?」
正解は「おまえ」だったらしい。
平助はさっきよりも顔を真っ赤にして、私を指さした。
「人様を指さしちゃいけません。」
「うっせえよ!
つか、な、なんだよその格好!!」
その格好って、何その言い方。
まるで私が変な格好をしてるみたいな。
「黒猫ですが?」
これが、今日でなければ私はただのコスプレマニアだ。
でも、今日はハロウィン。
これが当たり前、なのである。
「なんでっ、黒猫っ!?」
「魔女は千鶴ちゃんがやってるから。」
「じゃなくて!なんでっ!その格好っ!?」
「だから、仮装しろって話だったじゃん。
つか、そっちだって仮装でしょ?」
オレンジ色のパーカーを着て、紙で作ったジャックオーランタンのお面を頭に被ってる平助の姿。
ちょっと気合いなさすぎるでしょと突っ込みたい所だけど、だからといってカボチャをくりぬいて持ってくるのも一苦労
だし、それを被ってたら、どんだけハロウィン好きなのさって突っ込みたくもなるから、この位がいいのかもしれない。
「ちが、そ、じゃなく、てっ!」
何が言いたいのか分からない。
平助は私の格好を改めて上から下まで見るから、
「にゃん」
とポーズを取ってみせると、何故か平助はぶはっと変な咳を漏らした。
そんでもって口を慌てて押さえる。
え?なに?どした?
「‥‥鼻血?」
「ばっ!」
若いなぁ、24歳。
まるで初孫でも見るような目で見つめていると、その顔やめろと平助に怒鳴られた。
最近、カルシウム不足だと思いますよ、藤堂先生―
「‥‥で?」
「でって、なんだよ?」
ひょいと手を差し出すと平助は不審そうに眉を寄せた。
因みにちろっとその度に私の格好を見ては頬を染める。ういやつだ。
「トリックオアトリート。」
忘れられているような気がしたので再度催促。
「あ、ああ。」
言葉に途端に、何故か勝ち誇ったような顔で平助はポケットに手を突っ込む。
「すっげぇ、美味いの見つけたんだよ!」
さっきまで真っ赤になってろくにこっちも見られなかったくせに、単純。
だけど嬉しそうな顔に私もついついへぇと口角が上がった。興味津々だ。
「どんなやつ?」
「見てからのお楽しみっ‥‥って、こっちじゃないか。」
右のポケットには無かったらしい。ということで、反対の左のポケット。
「あれ?」
と思ったら無かったらしく、今度はズボンのポケット。
「‥‥平助。前々から言ってるけど、入れるところは決めて置いた方がいいと思うよ?」
こないだだって定期どこかいったって、喚いてたのに、と呆れたような声で言うと、
「わ、分かってるっての、つか!せ・ん・せ・い!」
と反論。
割と冷静だなぁと思いながら、そのお菓子が出てくるのをひたすら、待つ。
がさごそがさごそ。
待つ。
ぺたぺた、ぺたぺた。
待つ。
「‥‥‥‥‥‥‥」
やがて、平助の忙しなかった動きが止まり、徐々に顔が青ざめていく。
大丈夫?顔に血巡ってる?って聞きたくなるくらい、真っ青に。
因みにその表情は強ばってて、その顔に台詞をつけるとしたら、これ。
『やべぇ』
「‥‥ないの?」
静かな私の問いかけに、平助の肩がぎくりと強ばった。
「や、あの‥‥確かに、ここに‥‥」
右のポケットをぱしぱしと叩いてなんでないんだよと呻くように呟く。
無意識にがり、と歯を立てたらしい。
いい音がして、次の瞬間ふわりと、サイダーの爽やかな香りがした。
「平助、もしかしてと思うけど‥‥私にあげようと思ったのは、飴?」
「‥‥あ、ああ。」
「そして、もしかしてそれはサイダー味の?」
「‥‥」
なんで分かるんだ?と言いたげな顔を向けられて、私は溜息を零した。
多分あれだと思う。
「平助‥‥美味しいからって自分で食べたでしょ?」
「っ!?」
びくんと平助の身体が震えた。
図星って反応だ。
分かりやすすぎ。
「そ‥‥その‥‥」
まるで叱られた子犬、みたいな顔で恐る恐る、私を見上げる。
飼い主になったつもりはないけれど、そんな顔をされると、怒れない。
いや、怒るつもりは毛頭無いけど。
ただ、
「‥‥お菓子がないんじゃ仕方ないよねぇ‥‥」
にやり、と口元に笑みを浮かべた私に、平助はぎっくーんと背筋を伸ばして、凍り付いた。
そんな恐ろしい顔をしてたかな?涙目にさえなる平助に、私はわざと恐怖を煽るべくくつくつと笑ってみせる。
「大人しく、悪戯を受けて貰おうか。」
そう言って、がしっと両手でその頬を掴んだ。
ひ、と小さな悲鳴が上がったのは聞かなかったふりをしてあげよう。
「ちょ、、す、ストップっ‥‥」
オレ、まだ死にたくないとかいう台詞でも上げそうなそいつに、私は笑顔のまま宣告した。
「覚悟しろ――」
ころん、と口の中に転がるそれを満足げに舐めた。
「ほんとだー、これおいしー」
私の口の中でころころと転がるのはサイダー味の飴。
そいつの言うとおり、爽やかな甘さで美味しい。
「これ、どこで買ったの?」
出来たら箱買いしたいなぁなんて振り返ると、
「‥‥‥‥‥」
平助は、まるで魂でも抜けたかのようにころんと転がっている。
因みに何故か効果として、窓から光が差し込んで丁度スポットライトのようだ。
悲劇のヒロイン、ならぬヒーローといったところで、向けられた背中の哀愁が漂うこと‥‥
「そんなに落ち込むことないじゃんー」
「‥‥」
「そりゃまあ、美味しい飴を奪ったのは悪かったと思うけどさ。」
言葉に、ぴくりと肩が震える。
そう、
私は彼から飴を奪った。
半分に割れた、飴を。
彼の口の中から。
口移しで無理矢理ってヤツ。
無理矢理っていうか、平助は呆気に取られてたから無理強いでもないと思うけど。まあ、キスは無理矢理、かな?
でも、
「いいじゃん、別に。」
と私は思うのだ。
だって、私と平助は確かに生徒と教師だけど、同時に彼女と彼氏でもあるわけで。
キス、は、そりゃ初めてだったかもしんないけど、そんなに落ち込む事もないと思うんだ。
好き同士ならキスするのは当然で、ちょっと強引だったかもしれないけど、これで漸く私たちは初めてのキスを済ませら
れたわけで、
「‥‥もしかして、私とキスしたくなかったとか?」
「っ」
問いかけにがばっと平助が身体を起こして、
「そんなわけねえじゃん!!」
振り返り様に強く否定された言葉に、私はすごく嬉しいと思ってしまう。
思わず照れてしまうじゃんか、このやろ。
「‥‥あ‥‥」
その私に気付いたのか、平助は小さく声を上げ、視線を落とした。
中学生か自分ら、と突っ込みたくなるけど、二人して照れて、赤くなって、視線を落とす。
揃って沈黙だけど、気恥ずかしいその空気が心地よかったりもする。
「‥‥な、なあ。」
二人して俯いていると、平助が私を呼んだ。
なに?
と顔を上げれば、平助は私をじっと見たまま、なあ、ともう一度言った。
そして、何かを言いかけるように口を開いたけれど、言葉にはせず、代わりに、ず、ず、と膝をずって、私との距離を縮
めてくる。
「な、なに?」
悔しいかな、私の声が今度は上擦った。
どきどきと高鳴る鼓動が聞こえそうな距離で、平助はその、と赤くなった目元を一度落として、ちろ、と今度は上目に、
私を見る。
殺人的に可愛いその表情に、私がぎくりと肩を強ばらせば、
「トリックオアトリート。」
やっぱり甘ったるい、ぎこちないキスで仕返しをされた。
だけどそのキスのせいで心臓が破裂する‥‥と私は目を瞑りながら思った。
藤堂先生は、生徒であろうと先生で
あろうと変わらない(コラ)
でもこんな初な先生とか超かわいく
ないですか??
Happy Halloween2010(2010.10.31)
|