|
「トリックオア、とりー‥‥とぅわぁ‥‥」
出迎えたその人の姿を見た瞬間、決まり文句を放棄してそんな声を上げてしまった。
因みに視線は頭。
釘付け。
茶色い癖毛からはみ出しているのは、同じ色をした獣耳。
恐らく、犬。
「ヨクオニアイデ‥‥」
思わず棒読みになってしまったのは、決してそれが似合わなかったからじゃない。
むしろ、
似合いすぎて怖いからだ。
私の目の前にいる犬耳を着けているのは、大の男で、しかも二十を越えた教師で。
「ありがとう。」
犬なんて可愛いものかと思った撫でたら悪魔だったという――その人の名は沖田総司という。
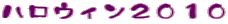
いや、確かに教師も参加とか言ってたけど、このイベント。
でもまさか、ノリノリで仮装までしてるとは思わない。
しかもこの、何に関しても「適当」っていうのがスタンスの‥‥とりあえず授業だけはまともにやってください、なこの
教師が、こんな面倒くさそうなイベントに、ばっちり仮装して参加、なんて。
大方屋上でサボってるかと思ったんだけど。
「‥‥先生、それ、今にも動きそう。」
もふもふした耳を指さして言うと、先生はまさか、と笑った。
「そんな高性能じゃないよ。」
「‥‥いや、性能云々じゃなく‥‥」
実際生えてそう?
いや、本来の姿が高校教師じゃなく、狼男だったら困るんですけどね!
因みに、カーデの裾から覗いているのは、同じ色をした柔らかそうな尻尾。
‥‥身長176センチのあるしかも二十を越えた男の頭から獣耳が覗いているのはある意味ホラーなんだけど、それが似
合うのがより恐ろしい所だ。
「属性は猫だと思うんだけど。」
「男は狼だよ?」
それはどのあたりがですか?というのはなんとなく怖い答えが返ってきそうで止めた。
そんな私をにこにこといつもの笑顔で、どうぞ、と準備室の扉を開けて招き入れてくれる。
準備室は先生のテリトリーだ。
自分の好きなように勝手に改造してしまっては、他の先生に怒られているようだけど、反省の色は一切、ない。
因みにそれを表すかのようにいつの間にかソファーとテーブルが増えていた。その上にはカップが二つ、並んで置かれて
いる。
珍しい。
他の教師さえ滅多に入れないのに、先客がいて、なおかつ、飲み物まで出して貰える人がいるとは思わなかった。
それよりも私がここに毎度招き入れられる事の方が不思議なんだけど、と思いながら、ふと忘れていた事を思い出して振
り返る。
「トリックオアトリート。」
気を取り直して、掌を上に向けて突き出せば、彼はにこりと笑いながら私の前を通り過ぎた。
華麗にスルー?
「はい。」
かと思ったら、テーブルの上のカップを一つ持ち上げて差し出される。
まさか私にとは思わなかった。驚いた。
カップからふわりと立ち上る香りはココアのそれだ。
「‥‥これが、お菓子の代わりって事ですか?」
「そういうこと。
君、あんまりお菓子とか興味ないでしょ?」
そりゃあ確かに。
残念ながら女の子の規格とは外れている私は、甘い物があまり得意じゃない。
飴以外のチョコとかクッキーとか、貰っても食べきれる自信はなくて‥‥正直このイベントも「悪戯」目的に参加してる
ようなものだ。
よく見てるなぁ、なんて感心しつつ私はカップを受け取った。
猫舌なので、良く冷まして、飲む。
ココアは、風味がとっても深くて‥‥だけど、甘さは控えめ。私好みの味だった。
更に感心。
すごいな、先生。
なんて思いながら二口目を嚥下していると、
「それにしても‥‥」
先生は私の姿を上から下まで見て、ふっと困ったように笑った。
「これまた魅力的な黒猫だね。」
「見事なコスプレでしょ?」
うん、と言ったきり、先生は私の一部分を見て、止まる。
凝視ってやつ。
「黒猫ってニーソ?」
「だったら随分とお洒落だな、と。」
「いや、随分とセクシーでしょ。」
ショートパンツと、ニーソの間。
俗に言う絶対領域を遠慮もせずにじーっと見て、先生は呟いた。
「おっさんですか?」
「失礼だな、僕はまだ26だよ?」
「いやでも、視線はおっさんと同じですよ。
実は、見た目若いけど、始40越えてるとか?‥‥おっさんですか?」
「君たち年代は40を越えたらおじさんになるんだね。覚えておく。
でも男なら普通そこを見ちゃうと思うけど?」
‥‥そうなのか?
一応女の子なので分かりません。
私は自分の絶対領域とやらをじっと見た。
とりあえず、なんとも思わない。思ったらどれだけ自分好きなんだと突っ込みたい所だけど。
あ、でも、千鶴ちゃんの絶対領域とかは見たいなぁ。
あの子色白いし、太股柔らかそうだし‥‥って、おっさんか!!
「‥‥それで、その格好で今日は学校を回ろうって言うの?」
ぽつんと零された問いに、私は首を捻った。
生憎とこれしかコスプレ衣装は持ってきてない。
「なにか問題が?」
私の返答に、先生は一瞬だけ、思い切り眉間に皺を寄せて見せた。
それはそれはもう不機嫌って顔で‥‥いつも笑顔のその人から想像できない。
むしろどっかの土方先生みたいです。
「そっか。」
だけど、すぐににこりといつもの笑顔に戻る。
「それじゃあ、僕のお願い聞いてくれたら出てもいいよ。」
いつから私は先生の許可がないと外に出られなくなったんだろうって発言に、今度は私の方が眉間に皺を寄せることになる。
どういうことだと口を開くよりも前に、彼ははい、と手を出した。
「トリックオアトリート。」
「‥‥‥‥‥‥」
私は無言で先生を見上げた。
因みにお菓子袋には、まだ、一個も入ってない。
これから増えるはずだったから中身は空っぽだった。
恐らく死ぬほどお菓子を貰うことになるだろうからと考えていたけども、あげることを考えていなかった。
さっきの『するめいか』が私の最初で最後の用意していたお菓子。
迂闊だったけれどそれを差し出した所でこの人が納得してくれるかと聞かれれば笑顔で却下されたと思う。それはお菓子
じゃないとかなんとか。立派なお菓子です!
「‥‥‥ええと‥‥」
困ったような顔でそう呟くと、先生の笑みが一層濃くなった。
そうなんていうか、
悪魔の笑み。
「先生‥‥狼男が悪魔に見えます‥‥」
「うん?お化けなんだから同じじゃない?」
「いえいえ、違います。っていうか、なんか近いんですけど‥‥」
近いというか、なんか、若干追いつめられているような気が。
と私がもごもごと呟くと、先生はにっこりと今度は一層眩しい笑顔――何故かそれがひどく恐ろしく見えるんだけど――で、
「そりゃ、お菓子がもらえなかったから。」
流れるような所作で腰に回された手が私との距離を一気に縮め、その手の大きさにどきりとする間も与えられず、高らか
に、宣言。
「悪戯するしかないでしょ?」
可愛らしく小首を傾げた狼さんに、私は見事に頭から食われた。
そりゃもうぺろりと。
「い、いたいけな高校生になにるすんですかぁああ!」
「君自分でいたいけって言っちゃうんだ?」
「ひどい、ひどすぎる!!」
こんな、こんなこと、と涙目になりながら押し上げられた服を下ろして慌てたように着衣を整える私に、彼は意地の悪い
それで覗き込んできて。
「酷いこと、してないでしょ?
十分優しくしてあげたつもりだけど?」
優しくするつもりなら普通はあんなことしない。
私は、心の中で叫ぶ代わりに彼が脱いだカーデをその顔に投げつけ、いたたと呻く隙に魔の手から逃れた。
立ち上がってすぐにかくんと膝が折れて、私は腰から下が満足に動かなくなっていることをこの時になって知った。
しかもその瞬間、あれの時みたいに中から何かが出てきたような感覚に、ぎょっとしつつ、深くは考えたくなくて、とに
かく這ってでも逃げようとすると、困ったような笑い声と共に足音が近付いてきた。
「逃げようとしても、だーめ。」
「ひゃぁっ!?」
大きな、逞しい手に掬い上げられて、また、ソファに埋められた。
因みにまだ新品らしく、独特なにおいがする。
それに混じる、私と先生の香りに、どきりとしていると、更に私の上にどさりと覆い被さる彼の温もりと移り香よりも強
い彼自身のにおいに痛いくらいに胸が高鳴る。
全開の胸元から漂うのは紛れもなく大人の、男の色気。
その胸にさっきまで抱きしめられていたかと思うと、一気に体温が上昇した。
気恥ずかしさを上回るのは、私の知らない感情。
それを認めたくなくて、私は頭を振った。
「や、だ、離してっ」
「駄目、離さない。」
「や‥‥ぅっ‥‥」
「今ここで君を離したら一生、僕の所に来てくれないでしょ?」
「あ、たりまえっ‥‥」
こんな酷いことをした教師の所になんて二度と来るものかと返せば、だから、と先生は遮った。
「離さない。」
「や、やだっ」
離してと言う声が震える。
本気で泣きそうになってる私を、先生はむっとした様子で見下ろした。
「なんで泣くかな。」
「な、泣かいでか!」
「泣くことないじゃない?
僕は痛くしてない。」
「い、痛み云々の問題じゃなくて‥‥」
「それどころか、君をめいっぱい気持ちよくしてあげたつもりだけど?」
気持ちよくなかったの?とか聞かれても答えられない。
まるで雪崩が起きたかのようで必死で藻掻いていただけだから覚えていない。ただあられもない声を上げさせられた事だ
けは覚えている。悲鳴ではなかった。痛くも、なかった。
でも、泣きたい。大泣きしたい。
理由は分からないけれど、と心の中で呟くと、ちゅとこめかみにキスをされると背筋に震えが走ってまともに言葉を紡ぐ
ことも出来ない。
やだ、これ、なに。
困惑する私を覗き込んで、先生はにっと口元を歪めて笑った。
「あんなに善い声あげちゃうくらいだから‥‥良くないはず、ないよね?」
「しらなっ‥‥」
「僕にもっとってせがんだくせに?」
言葉と同時に、こめかみから耳元まで唇が滑り落ちれば、わけの分からないものにガクガクと身体が震えた。
その間に折角下ろした服の端を持ち上げられて、大きな手が滑り込んでくる。
熱を持った手は悪戯でもするように私の肌を擽って、だけどこみ上げてくるのは笑いではなく、紛れもない快感。
「だ、だめっ」
浮かんだ涙を唇で吸われて、恥ずかしさのあまりに大泣きしたくなる。でも泣いたらそれも全部彼に吸われるだけだと思
ったら憤死しそうだ。
だめと胸を押し返したら代わりに太股を撫で上げられた。
ざわりと肌が泡立ち、息が止まる。
身体が震えたのが期待のせいだと思うと、悔しかった。
「それに、酷いのは君の方。」
ちゅ、ちゅ、とこめかみに、頬に、キスを何度も落としながら不満げに先生は呟いた。
言うに事欠いて、被害者である私に罪が在るというのだ。
「な、んでっ」
私何も悪いこと、と涙目で見あげれば、不満げなその瞳に先生は今まで見たことがないくらい色っぽい、だけど切ない色
を浮かべていて、こう、言った。
「君が。
いつまで経っても僕の気持ちに気付いてくれないのが悪い。」
あんなにいっぱい、
君に気付いて欲しくてやってるのに――
先生の愛情表現は分かりにくいです。
そう、私が反論出来たのは、それからまた二時間ほど経った後のこと。
沖田先生、狼男よろしく辛抱できずに
喰っちゃった、的なお話。
なにげに沖田先生を書くと、色々と、
エロスな方向に進みます。楽しいです。
Happy Halloween2010(2010.10.31)
|