|
「トリックオアトリート!」
「‥‥」
玄関を開けて、別の人が出てきたらどうしようかという心配は、見慣れた顔に出迎えられて綺麗さっぱり消え去ったんだ
けど。
代わりに居たたまれなくなるくらいの凝視と、沈黙に、やっぱり来るんじゃなかったかと後悔したその瞬間、
「新聞なら間に合ってる。」
「いや、ちょ、閉めないで、土方君!!」
バタンと閉められた扉に縋り付きながら、世の男性はこんな孤独感を覚えながら奥様に閉め出されるのかな、なんて思った。
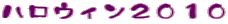
5分と経たずに隣の部屋のドアが開いて顔を出した隣人(男)がうるせえぞと怒鳴り掛けた口が開いたまま、塞がらない。
とんでもない羞恥プレイに私はお願いだから開けてと懇願した瞬間に扉が開いて、隣人を一瞥した次の瞬間、無言で引き
ずり込まれた。
心底呆れたような声で言われた「近所迷惑」って。
全くその通りですが、ちょっと酷くないだろうか。
折角、ここまで恥ずかしい思いをして来たのに。
「頼んでねえよ。
つか、なんで家まで来るんだよ。」
そうブツブツと呟くと、これまた冷たくそう返された。
「だって、今日休んでるって言うから。」
折角のハロウィンパーティだっていうのに、彼は欠席で。見るからに具合が悪そうではないので恐らくサボリだ。
テーブルの上に教科書やら参考書が広げられていたってことは、サボって受験勉強というところなんだろう。
熱心と誉めるべきか、サボるなと叱るべきか‥‥
「参加すれば良かったのに。」
楽しかったよ?と言うと、彼に下らねえと一蹴されてしまった。
まあ確かに。
お化けの仮装してお菓子を強奪して楽しむ土方君の姿は想像できない‥‥っていうか、もうもろマジなカツアゲみたいです。 犯罪のにおいがします。微笑ましいイベントになりません。
「‥‥なんか言ったか?」
「いえなんでも。」
私は頭を振った。
ったくと呟きながら彼は私の前に湯気の上がるカップを置いてくれる。
コーヒーだ。有り難い。
「こんな格好で来たもんだから、身体冷えてたんだよね‥‥」
いただきますと先に言って、一口飲む。
相変わらずイイ豆を使っているようで風味が素晴らしい。
「‥‥まさかと思うが。」
その呟きに、土方君は眉間の皺を濃くした。
「てめえ、その格好で来たのか?」
「その通り。」
答えに、信じられない、という風に彼は顔を顰めた。
いや、まあ自分でもどうかしてる、とは思うけど、さ。
でも一応コート着てきたし、猫耳尻尾は、玄関来るまでは外してたし。
そりゃまあ、この年にしてニーソ、ってのは死ぬほど恥ずかしかったんだけどね‥‥通行人には私の実年齢が知られてい
なくても。
「‥‥てめえには少し危機感とかそういうのはねえのかよ。」
はふ、と溜息交じりに呟かれ私は危機感?と首を捻った。
なんで外を歩くくらいで危機感覚えなきゃならんのよ、私、誰かに狙われてるわけでもないのに。
「違う。
その格好だからだろ。」
「‥‥え?なんで?」
心底分からないって顔をしたら、苦虫を噛みつぶしたような顔をされて、
「もういい。」
おまえに話しても無駄だと言わんばかりに話題を強制終了された。
そのまま不機嫌そうな顔のままでどっかと向かいに腰を下ろすと、同じようにコーヒーを飲んで、で、と視線で促す。
「なんの用だよ。」
「トリックオアトリート。」
「‥‥まさかてめえ、こんな時間にここに、菓子をせびりに来たってんじゃねえだろうな?」
「ハロウィンにそれ以外どうしろっていうのさ。」
私の尤もだと思う反論に、眉間にものすっごい皺。
それから、思いっきり溜息。
「今、心の中で付き合いきれないって思った?」
「思ってねえ。
下らねえと思った。」
尚悪い。
「悪いけど、暇じゃねえんだよ。」
土方君は言って立ち上がる。
勉強の続きをするつもりか、コーヒー片手に参考書の前に座り直すと、ぺらとページを捲り始めた。
客人を無視するらしい。
「ちょっとー」
「あ、勝手に出てってくれ。」
断りはいらねえよと言われて私はあきれ顔で立ち上がる。
彼はかりとペンを走らせながら、付け足すように言った。
「隣のヤツには気を付けろ。
今月に入ってもう5人違う女を連れ込んでる。」
「それはどうでもいいでしょうがー」
私の反論にちっと舌打ちが返ってきた。
どうでもよくねえよとか不満げに聞こえたのは、気のせいか?
そんなことよりも。
「たまにはさ、遊んだって罰当たらないと思うわけですよ。」
追いかけるように私は彼の傍に近付いていった。
「灰色の受験生に、遊べって?」
彼は嘲るように呟く。
「こちとら将来掛かってるんだぜ?」
「いやまあそうなのは分かるんだけど、それでもほら、息抜きしないとパンクしちゃうわけで。」
「んな格好してるヤツに息抜きとかパンクとか言われても、ねぇ。」
「笑いたければ笑ってください。
でも、その前に一個だけ付き合って。」
私はぐいっと強く椅子の背を引いた。
ぐるんと90度回転し、彼の身体は強制的に私に向けられる。
「んだよ。」
不機嫌な瞳を真っ向から受けて、私はくそ真面目な顔で、言い放った。
「トリックオアトリート。」
「‥‥‥‥‥‥‥」
切れ長の瞳が、一層、細められた。
めっちゃ、睨み付けてるって顔だ。
こんな下らない事に付き合う義理はない‥‥って感じ。
でも、ここは譲れない。
折角のイベント、彼にだって少しでいいから楽しんでもらいたい。
怯まずに、私は瞳を見つめて、もう一度。
「トリックオアトリート。」
これをしなければ今日は終われない。
私も、それから彼も。
だって、今日はハロウィンなんだから。
ばち、ばちと火花でも散るかのようににらみ合うこと、数分。
そんなに長い時間ではなかったのかもしれないけれど、溜息でそれはうち破られた。
「答えれば、納得すんのか?」
「はい。」
くそ真面目な顔で頷くと、やれやれと言った風に肩を竦められた。
生徒に呆れられる先生ってどうなんだろうかと思いつつ、彼の反応をじっとひたすらに待った。
やがて、
薄い唇の端がゆっくりと引き上げられ、
意地悪く微笑みかけられた。
「‥‥じゃあ、トリックで。」
彼はそうリクエストした。
トリートではなく、トリック。
trickとは正確には「企み」とか「ごまかし」とかいう意味だけど、今ここでは若干ニュアンスが違う。
「お菓子くれなきゃ悪戯しちゃうぞ」
つまりは、
お菓子ではなく、悪戯を所望した。
「え?」
まさか、そっちを選ばれるとは思わずに‥‥そりゃ悪戯なんて好きこのんでして欲しい人なんていないはずだから‥‥目
をまん丸くすると、土方君はどうした?と挑発するような眼差しを向けて言った。
「悪戯‥‥しねえのか?」
悪戯を催促され、私の方が困惑してしまう。
「え、だ、だって‥‥」
「生憎と、うちには菓子なんてねえからな。
差し出すもんがねえんだから甘んじて悪戯されてやるって言ってんだよ。」
そう、なんだけど、いや、違う。違う?
「なんだよ、とびっきりの悪戯でも考えてたんじゃねえの?」
きしと椅子の背が軋んで彼が身を乗り出す。
そうすると距離が近付いて、いつもとは違って見上げる、しかも、上目遣いで、悪戯っぽく見られて、普段とのに戸惑っ
ている間に、
「っ!?」
腰を攫われた。
ぎし、と今度は重たい音がして、私は気付くと彼の膝の上にこう、跨るような格好で乗っかっていて‥‥
「ちょ、ちょ、待って!?私が悪戯するんだよね?!」
「そうだ。」
「な、なのになんでこんな状態っ」
逃げようと肩を押し返すんだけど、男の子の力に敵うわけもなく、強く引き寄せられると足を更に広げざるを得なくて、
なに、この体勢!?
しかもそれだけじゃなく、引き寄せたまま、土方君は背ける私の首筋に唇を寄せてくる。
「ま、マテマテっ!おかしい!明らかにおかしいからっ!」
「おかしかねえだろ。
ほら、早く悪戯してくれよ。」
「ちょ、その発言卑猥!セクハラで訴えるよ!」
「はいはい、分かったから。」
ぐ、と更に腰を引かれて、ぴたりと、私と彼の身体が密着する。
すると、私の身体を押し上げるように、身体の下に、固く、熱いものが、当たった。
「ひ‥‥」
と唇から悲鳴みたいな声が漏れた瞬間、土方君は私を見上げて、
それはそれは壮絶な色気を放つ濡れた眼差しで、表情で、強請った。
「Play a trick to me。」
それがやたら発音が良くて、むかつくと、私は思う。
「‥‥お願いだから、さぁ‥‥」
私は半泣き状態で彼を見る。
勉強を中断されたはずの彼は上機嫌で私を見下ろして、なんだよ、と清々しいまでの笑みを浮かべた。
いつもはきちんとボタンを留めているシャツがそりゃもう目に毒だよというくらいに全開だ。
まだ色づいている肌から感じる色気にぎくりとして、目を逸らしながら私は言った。
「それ、使うの止めてください。」
それ?と彼は首を捻る。
分かってる顔だ。くそ、意地悪な顔なのに、なんでそんなに綺麗なんだ。
私は涙目で身体を起こし、申し訳程度に掛けられた彼の上着を引っ張り上げながら、だから、と目線だけで訴える。
「それ。」
「‥‥それじゃわかんねえよ。」
「分かってるくせに!!」
「だから、それって?」
「そ・れ!」
私は叫ぶように声を張り上げて、びしっと指さした。
それ、というのは彼が今、まさに座っている回転式の椅子の事だ。
「捨ててください!!」
「なんでだよ?
これ、なかなか弾力があって、長時間座ってても疲れない優れものなんだぜ?」
背凭れにぎしりと凭れ掛かりながら、彼は長い足をゆったりと組み替える。
なんでそれだけで様になるんだろうかと、悔しさ半分、恥ずかしさ半分で睨みつけると、彼はにっと双眸を細めて笑った。
絶対、私の言いたいこと分かって、やってるな、こいつ。
「う〜〜!!」
悔しくてぎりぎりと奥歯を噛みしめる私に、ああ、と彼は思いだしたように声を上げた。
「安心しろ。」
なにがだよ、と心の中でだけ突っ込む。
言葉に出来なかったのは彼が申し訳程度に引っかけていたベルトを外したからだ。
ぎょっとして慌ててもう無理、駄目、と首を振る私を、それはそれは心底楽しそうに見て、その手を私へと伸ばす代わり
に自分がお尻の下敷きにしているクッションを撫でながら、こう言った。
「時々思い出して、有効利用させてもらうから、さ。」
「今すぐ燃やせ!!」
何に有効利用かは、怖くて聞けなかった。
土方君は、相手を先生だと思っていない
ように見えて本当は相手が「教師」という
のを一番自覚しているタイプ。
だからこそ意地悪になる。
Happy Halloween2010(2010.10.31)
|