|
学校に着たら突然、頭から水を被らされた。
一体何事かと驚いている間にも、同僚が「大変だ、すぐに着替えなくちゃ風邪をひくぞ」と大根役者そのもののわざとら
しい口調で言って、私に『それ』を押しつけて、シャワールームへと突っ込まれた。
とにもかくにも濡れたままじゃ風邪を引くのは目に見えているのでシャワーを浴びて、着替えようとした瞬間、私はして
やられた事に気付く。
今日は、ハロウィンだった。
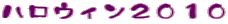
「先生、こんな所で何やってんだ?」
「うぉう!?」
絶対見つからない場所、と言えば社会科資料室。
教師でさえ出入りの少ないそこは、あまりの埃臭さに生徒もサボリの場として使われないような所だ。
だから誰も来ないと思ってたら、思ったよりも簡単に見つかって、私はびくっと飛び上がった。
慌てて振り返ると、戸口に立っていたのは我が校でも一番の身長を誇る生徒。原田左之助。
因みに学区内では有名なイケメン。
18歳にしとくのが惜しいほどの大人の色気むんむんの生徒だ。高校生のくせに。
「‥‥は、原田君か‥‥おどかさないでよー」
ほぅと溜息を零しながら告げると、彼は悪い悪いと苦笑で謝って、戸を後ろ手に閉めてとことこと近付いてくる。
あれ?と私はその格好を見て不思議に思った。
「仮装は?」
今現在、我が校で仮装をしていない生徒、教師を含め、恐らく一人もいないだろう。
今日はハロウィンパーティと言うことで、全員が全員、なんらかのお化けの格好やら意味不明な格好で校内を闊歩しては
お菓子の激しい奪い合いを繰り広げている。
だというのに目の前の原田君はいつもの学生服だ。そしていつものようにタイは緩めて第二ボタンまでが開けられている。
「‥‥もしかして、学生の幽霊?」
わかりにくすぎるんだけど、と突っ込むと彼は違うと頭を振った。
「や、本当は骨Tシャツを着る予定だったんだけど、さ。」
頭に、骸骨の被り物して、と言う。
どうやら彼はスケルトンになる予定だったらしい。
「でも、女子に却下された。」
「あー、そりゃ分かるなぁ。」
女子が口を揃えて「駄目」という姿が目に浮かぶ。
だって、被り物なんぞを被ってしまったら、その見目麗しいお顔を拝見することは出来なくなるわけで‥‥
「君にお似合いなのはドラキュラ伯爵かな。」
「それ、女子にも言われた。」
美女の血を啜るイケメン吸血鬼‥‥自ら血を吸ってと志願する女の子は多数だな。
モテ男め。
「‥‥ところで、先生こそなんだよその格好。」
彼は私の格好に気付いたらしい。
くそ、机の下は見えないからあまり気にならないかと思ったら、目聡い。
とはいえ、頭にあんなもんつけてりゃバレバレだわな。
「猫?」
頭に生えている三角に尖った耳をちょいと、指先で摘んで訪ねる彼に私は沈痛な面持ちで頷く。
「魔女に使える黒猫だそうだ。
嵌められて着せられた。」
「‥‥‥へえ‥‥」
まったく、と私は呆れたように溜息を零して、手にしていたペンを放り出す。
代わりにペットボトルを掴み上げて、やけ酒を煽るみたいに飲んだ。
「だいたいさー、おかしいと思わない?25にもなってコスプレとか。」
「いやでも、全員やってるし‥‥」
「だって、猫だよ?猫?」
私は難しい顔をする。
正直、自分の格好を鏡で見るのはおぞましすぎるのでどうなのかというのは分からないが、想像するととんでもなく恐ろ
しいと思うんだ。
いい年した大人が、猫のコスプレ、なんて。
「そういうのをしていいのは10代の可愛い子だけでしょ。」
若いだけで許されるって羨ましい。
私らの年齢でやると‥‥なんというか、色々痛い。
イメクラか!って感じだ。
「別に良いんじゃねえの?」
「原田君。女の人なら誰にでも優しくしていいってものじゃないんだよ?」
時には現実を突きつけてやらなければいけない事だってあるわけ、で、
と続ける私を遮って、原田君は妙に納得したように呟いた。
「先生、似合ってるし。」
この天然タラシ――
思わず口から出そうになった言葉を飲み込み、代わりに私は疑わしいものを見るように彼を見た。
彼はどうした?と首を捻る。なんでもないと頭を振った。
天然には何を言っても無駄だ。
「‥‥ところで、一体何の用?」
こんな誰も来ないような所に何か用があるのだろうかと訊ねると、彼は、ああ、と呟いて、
「サボリ。」
と悪びれなく言うのだ。
教師の前で、サボリ。まあ、いいけどね、私も似たようなもんだし。
「‥‥つか、学校全体で公然コスプレにカツアゲ‥‥って。」
「身も蓋もねえような事言うなよ。」
「だって、お菓子くれなきゃ悪戯するぞって‥‥ある意味脅迫。」
これのどこに夢を持てばいいんだろう?日本人だから分からないのかな。
呟く私に、ま、と彼は私の格好をちろっと見て、
「‥‥一部の人間にはロマンがあるんじゃねーの?」
と答える。
どゆこと?
「雪村先生ー」
訊ねようとしたらタイミング良く、廊下で私を捜す声が聞こえて、ぎくんっと私は肩を強ばらせた。
あの声は数学の新田先生。
やばい!私探されてる!?
逃げないとっ
「ちょい待ち。」
慌てて立ち上がって荷物そっちのけで、窓から逃げようとする。
相当テンパってた。
開けた窓の下、地面は数メートル下。ここ3階でした。
「いくらおまえが運動神経良くてもこっから出たら怪我するだろうが。」
「そうでした!ってそうじゃない!」
冷静な原田君の突っ込みにくるりと振り返って、どうにか逃げる方法は?と訊ねると、彼はにっと口元に笑みを浮かべて、
「ほら、ちっとこれ被って奥に隠れてろよ。」
ブレザーを放り投げて寄越して、棚の奥を顎で指す。
私は慌てて首を縦に振って奥へと逃げ込んだ。
棚の向こうへと回って、腰を下ろす。
と同時に戸が開いた。原田君が外に出た、のかな?
「‥‥っ」
戸を開けた瞬間にひやりと冷たい空気が床を這うようにして流れ込み、しゃがみ込んだ私はその冷たさにぎくりと肩を強
ばらせた。
それに相反して手に持っていた彼のブレザーは暖かい。
なるほど、どうしてこれを寄越したか‥‥というのが分かったぞ。
原田君ってばやっさしー
私女で良かった、としみじみ思いながらブレザーを羽織らせて貰った。
脱ぎたてだから、彼の温もりが残っているようで‥‥暖かかった。
男の子ってそういえば女の子よりも体温高いよなぁ、羨ましいなんて思っていると、ふいにふわりと香るのは香水でも洗
剤でもない独特な香り。
それを体臭という。
男子高校生なんて汗くさいばっかりだと思っていたけれど、決して嫌なにおいではなかった。
石鹸か何かと混じったそれは、汗のにおいとは違って、ちょっと、甘い。
だけど、女の子のように甘いわけじゃない。
やっぱりそこは男臭さを感じるものがあって、
「‥‥‥」
私はそっと目を閉じてみた。
そうすると感じるのは、彼の温もりと、それからにおいだけ。
今、目の前に彼はいないけれど、まるで彼の腕に包まれているみたいで‥‥
彼の腕の中にいたらこんな感じなのかなぁ、なんて思いながらそっと私を包むそれを抱きしめるように自分の腕を抱くと
すぐ近くでふっと笑い声が聞こえた。
「抱きつくんならそれじゃなく、実物にしてもらいてえもんだな?」
「っ!?」
ぎょっとして目を見開くと、すぐ傍に彼の顔。
思わずうわぁと叫びそうになったのを、原田君が慌てて「しっ」と鋭く声を上げて私の口を手で塞いだ。
「まだ、新田が外にいる。
声なんか出したらみつかっちまうだろ?」
そ、そうでしたー
小声で言った彼にこくこくと頷きながら分かったと示すと、とりあえず口を覆っていた手だけは離してくれた。
だけど、
「あ、あの‥‥原田君?」
距離は相変わらず近いまま、だ。
こう、額をこつんと合わせるような距離で見下ろされ、私は居心地の悪さにええとと困惑した声を上げる。
そんな私に気付かずにか、
「教師総出でおまえの事、探してるらしいぜ。」
と彼は言った。
ああそうですか、探されてるんですか。なんで探されてるんだ?っていうか、この状況なんなんだ?
「みんなおまえのその格好を拝みてえみたい、だな。」
「え、はぁ、そうですか‥‥」
「まあ、よく似合ってるし?」
「‥‥あ、ありがとう‥‥ございます?」
「見せびらかして歩きたいくらいに可愛いんだけど、な。」
長い足がまるで私を挟むようにして立てられて‥‥いや、これ挟むっていうより、囲むっていう方が正しくない?
「あの、その、原田君、ちょっと‥‥」
離れてくれないかなぁ?とか‥‥
でも、
と呟く声が耳元に降ってきた気がしてぎょっとしていると、香りが一層強くなった。
「っ!?」
理由は、その腕の中に閉じこめられたから、だ。
「ちょ、原田くっ‥‥」
何この状況なんなの?
と慌てて顔を上げれば目の前には逞しい胸板。シャツ越しでも感じる体温と逞しさに、更にぎょっとして顔を上げれば私
を見下ろす双眸とぶつかった。
「あっ」
見なければ良かった‥‥と思った。
見なければ、
私はその熱に、欲に、囚われる事はなかったのに。
「誰にも、見せてやらねえ‥‥」
原田君は、何かを堪えるように双眸を細めた。
高校生のくせになんて表情をするんだと思うくらいに、色っぽくて切ないそれに、私の胸はわけもなく高鳴った。
苦しくて、喘ぐ。
漏らした吐息に、彼の双眸が一層細められて、同じような、だけど、それよりも熱い吐息が落ちた。
「」
先生でも雪村、でもなく、名前。
教師を名前で呼び捨てとはどういう了見だ?
そう、頭の片隅で思うのに、名前を呼ばれただけで痛いくらいに胸は高鳴り、期待に心が揺れる。
心が揺れた時点で、私に逃げ道は、ない。
「っ‥‥」
甘受するように目を閉ざせば、息を飲む音と、続いて苦しそうな吐息が零れた。
「トリックオアトリート。」
「え、な、に?」
泣きたくなるような快楽に、必死で逞しい身体にしがみついていると、唐突にその言葉を囁かれた。
言われた意味が分からなくて見下ろすと涙で覆われたそこに映り込むのは色っぽい原田君の顔だ。彼は悪戯っぽく笑って
いた。
「一応、聞いてからの方が良かったかな、と思って。」
「なに、を‥‥」
「お菓子くれなきゃ、悪戯するぞって‥‥」
ハロウィンの決まり文句を口にしながら、彼は突き上げてきた。
あ、とか細い声が上がって、瞼の裏がちかっと明滅する。
睨み付けると彼はにっと艶っぽく笑って、苦しげな吐息を漏らした。
「つっても、悪戯で済ますつもりは‥‥ねえけど、さ。」
当たり前だ。
こんな事を悪戯にされたら私だって堪ったものじゃない。
私は心の中で告げる代わりに、ぎゅっと背中に回した腕に力を入れた。
そのついでに身体に力が入って締め上げると、う、と彼が呻く声が聞こえた。
片目を瞑って私を見上げるそこに、余裕は、ない。
今まで好き勝手翻弄してくれた彼にそんな顔をさせられたことに優越感を覚えながら、私は薄らと笑みを浮かべて言った。
「トリックオアトリート。」
彼のポケットに入っているのは携帯と、ガムの包装紙だけ。
それを知っているからこそ告げる言葉に、原田君は驚いたように目を見開いて、
「お好きにどうぞ。」
結局、好きにされるのは私の方なのは目に見えているのに――
原田君はモッテモテの男の子です。
他校の生徒とかから毎日のように告白
されてるんだけど、それでも先生に片思い
してたらいいなぁと思う。
そんでもって実は機会をうかがっている、と。
Happy Halloween2010(2010.10.31)
|