|
きっとそれは運命というものだったのだろう。
誰にも変える事の出来ない運命。
産まれた時から出会うように決められていたのだ。
そう、運命の人と赤い糸で結ばれるように強く惹かれあうように出来ていた。
産まれた年も、場所も、何もかもがまるで違う。
それでも彼らは出会った。
小指にきつく巻き付けられた、鮮やかな赤い色をした糸によって引き寄せられた。
それは縁なのか。
それとも、彼らを縛り付ける鎖なのか。
血の糸は複雑に絡みあい――解く事は叶わない――
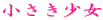
1
文久四年、一月――
吐く息はすっかり白く、空気も刺すように冷たい。
襖を開けて空を見上げると、雲一つ無い綺麗な青空が広がっていた。
あまりにいい天気だ。つい浮かれて外に出掛けてしまいたくなる。
しかし、
――ちり、
その瞬間、肌を鋭い針で刺すかのような鋭い視線を感じた。鈍い千鶴でさえ感じられる程あからさまな殺気。
姿を探す事は出来ないが、誰ぞが物陰から自分を見ている。否、見張っているのだ。
千鶴は溜息を零し、己の足下を見下ろした。そこにはなにもない。自由のはずの足下は、しかし誰にも見えない枷が嵌められていた。
「無理……だよね」
彼女は囚われの身の上だったのである。
千鶴が屯所で暮らすようになって、七日が過ぎた。
この屯所に連れてこられた時のように拘束されてという事は無くなったが、あの時と変わらず不自由な生活を強いられていた。
とは言っても部屋も一つ与えられたし、食事もきちんと食べさせて貰っている。ある程度の自由な時間も貰っていたが屯所内に女を置く事は許されないという事で男装の姿のままだし、相変わらず邸から出る事はできない。
何より辛いのが、屯所内を自由に出歩く事が出来ないと言う事だ。部屋を出る時は必ず誰かが監視についてくるのである。因みに先程視線を感じたとおり、部屋にいる間も誰かに見張られていた。最初に脱走しようとしたのがいけなかったらしい。随分と警戒されているようだ。
ずっと見張られているというのは正直良い気分はしないが、殺される一歩手前だった事を考えればずっとずっとましな待遇なのだろう。
殺される一歩手前だった彼女が何故生かされ、しかも彼らに保護をされているかというと、父『雪村綱道』の娘だからだ。どうやら父は新選組に出入りしていた事があり、彼らも父の行方を追っているらしい。だが数回しか顔を合わせた事がない彼らには父の顔がよく分からないらしく、ならば知った人間に一緒に捜してもらえば好都合という事で千鶴はお咎めなしの上に彼らに保護して貰うという事で落ち着いたのだ。
お咎めなしなのは有り難いけれど、彼らも捜しているという事に些か不安を覚える。なんせ彼らは人斬り集団。そんな彼らと蘭方医の父がどんな関係があったというのだろう。まさか自分と同じでまずいものを見てしまったのではないだろうか?
「だ、だめだめ!」
ふるふると千鶴は頭を振って嫌な考えを払いのける。
どうにも一人で部屋に取り篭もっていると悪い事ばかり考えてしまう。閉じ込められ、監視をされて気が滅入っているせいだ。
だから気分転換に外に出ていきたいのだが、
「無理、だよね」
また先程と同じ言葉が漏れた。
誰も千鶴の我が儘などを聞いてはくれない。聞いてくれるはずもない。だから今日もまた大人しく部屋に閉じこもっているしかないのだ。
そんな毎日は非常につまらないものだった。
一人で閉じこもっているのはつまらないが、たまに幹部の人間が顔を出してくれる事もある。元気にしているかと気に掛けてくれる人もいるし、中には話し相手になってくれる人もいるのだ。
でも、それも監視の一環だと思うと切なくなった。
つまりその楽しい会話も仕事の一環。その会話から何か情報を得られないかと探っているのだ。
所詮自分は『綱道を捜す為の道具』でしかないということ。
その事実を知ってしまうと、とても寂しかった。
それでも誰かに話し相手になってもらいたい。そう思う程に千鶴は孤独を恐れていた。
――不意にすたすたと足音が近づいてくる。
その静かな足音で、少なくとも気軽に声を掛けてくれるあの三人組ではない事を察した。となると残りは……
「っ」
千鶴は身体を強ばらせ、慌てて障子を閉める。
そうして部屋の真ん中で正座をして、自分は疚しい事などなにもしていないと言わんばかりに姿勢を正した。
別に構える必要などはない。悪い事などはしていないのだから。逆にそんな態度を取れば怪しまれると分かっているのだが、条件反射でつい自然と身体が強ばってしまうのだ。一歩間違えば殺される所だった。それを考えれば少女が構えてしまうのも仕方のない事。
足音が部屋の前で止まる。千鶴は緊張のあまりにひくりと喉を震わせ、
「ちーづるちゃん?」
ひょこと顔を出したその人を見て、千鶴の身体からは一気に力が抜けた。
「さん」
ほう、と安堵の溜息を漏らして表情を和らげる彼女に、は苦笑を浮かべてみせるのだった。
「そんな構えなくていいのに。あ、入っても良いかな?」
「は、はい! 勿論です!」
いつものように気さくに声を掛けてくれるに、千鶴は満面の笑みで答える。
お邪魔しますと断りをいれて入室すると、千鶴の前にとすと腰を下ろした。そういえばお邪魔しますと声を掛けてくれるのはくらいなものだろう。そもそも他の幹部は千鶴の部屋にも入ってこない。外で立ち話をする程度だ。
「そんなに構える程、他の連中は千鶴ちゃんに厳しい?」
「あ、いえ、厳しいというか……」
その、と千鶴は口籠もった。
可哀想な質問をしただろうか。もし厳しかったとしても千鶴が言えるわけもない。
は苦笑を浮かべながらそうだよなと、答えられない彼女の代わりに呟いた。
「総司は性格悪いし、一は無愛想だもんな」
「……」
頷く事は出来ない代わりに、千鶴は無言で視線を伏せた。
やはりあの二人か、とは苦笑を浮かべた。確かに、あの二人は千鶴にとって怖い人だろう。特に沖田だ。斎藤はこちらが間違った事さえしなければ基本何も言ってきたりはしないだろうが、沖田は違う。意地悪な事を言って人を困らせるし、からかうし、すぐに「殺す」「斬る」と物騒な事を言う。
因みに、鬼の副長は斎藤や沖田に感じる「怖い」とは別格だ。
もう睨まれただけで竦み上がって無きそうなる程に、恐ろしい。その眼光だけで人を捻り殺せそうな程、彼の眼力というのは凄まじいものがあった。
勿論怖い人だけではない。原田や永倉のように気さくに話しかけてくれる人もいるが、それでも時折疑いの眼差しを向けられている事があって千鶴は落ち着かない。
だから千鶴が警戒しなくていい相手は、3人だ。
一人は新選組局長である近藤。
元々近藤は千鶴に対しての警戒心は皆無だ。そればかりか彼女の境遇を心の底から可哀想だと思ってくれている。新選組の局長であるのは分かっているが、彼のおおらかさに何故か安心してしまうのだ。
二人目は八番組組長である藤堂だ。
彼は歳が近いというおかげと、元より人なつっこい性格をしていたおかげだろう。早々に警戒心を解いてくれた彼は、今では友達のように話しかけてくれる。
そして、3人目が――だ。
最初に土方の右腕と紹介された時にはあの鬼の副長同様に恐ろしい人かと震え上がったものだ。しかしその逆で、いっそ清々しいまでの爽快さと優しさを兼ね備えた人だった。
元々面倒見が良い性格をしているのだろう。新選組で預かると決まってから、一番気に掛けてくれたのはだった。
「さん、何持っていらっしゃるんですか?」
ふと、が手に持っている何かに気づいて声を掛ける。
白い包みを大事そうに持っていた。
「ああ、これはね」
はにこりと笑い、包みを開いてこちらへと差し出してきた。
その中にあるのは色とりどりの、可愛らしい菓子である。
「金平糖?」
「うん、丁度近藤さんに貰ったから、一緒に食べようかと思ってね」
「え! でも、金平糖なんて……」
一緒にと差し出されて千鶴は慌てた。
金平糖は高価な菓子だと千鶴も知っている。とても一緒に、と軽々しく食べられるものではない。
そもそも表面上は客人ではあるが、千鶴は監視されている人間に過ぎない。今だってただ飯食らいの居候の身分だというのに、こんな高価な物まで貰うわけにはいかないだろう。
「うん、でもさ。一人で甘い物ってのも寂しいんだよ」
「で、でも」
「だから一緒に食べてくれると嬉しいんだけどな……ってことで、あーん」
「え!?」
悪戯っぽい顔で摘んだ薄紅色の金平糖を差し出され、千鶴は驚きに声を上げてしまった。
まさかそんな事をにされるとは思っておらず、でも、あの、と目を見開いたまま、言葉にならない声を上げてどう対処したものかと必死で悩んでいる。
はにこりと満面の笑みを浮かべた。
「あーん」
「……」
何故だろう。優しい声音にそれ以上拒む事が出来ない。
まるでには背いてはならない。どんな命にも従わなければならないとそう思わせるのだ。それは命令でも何でもないのに。
「あ……あー……」
顔を真っ赤にした少女は目を瞑り、おずおずと小さく口を開いた。
沖田ならばきっと意地悪をして口に入れてやらないのだろう。そしてその様子を見て嗤っているに違いない。いや、下手をすれば別の何かを放り込まれるかもしれない。
そんな簡単に目を瞑ってはいけないよ。何をされるのか分からないのだから。
は内心でだけ呟いて、彼女の口の中に一粒、優しく金平糖を転がしてやる。
「おいしい?」
かり、と固い音を立てて砕けた金平糖はふわりと仄かな甘さを口いっぱいに広がらせた。
途端赤い顔が嬉しそうに緩んだ。久しぶりの甘い菓子は、いつもよりも美味しく感じた。
「おいしいです」
「うん、それは良かった。ああ、そうだ、一緒に庭を眺めながら食べない?」
部屋の中だと味気ないだろう、とが提案してくる。これにもまた千鶴は驚いてしまった。
必要最低限部屋から出るなと言われている千鶴は躊躇う様子を見せたが、は構わずにふすまを大きく開け放つと少女の手を取って縁側へと出た。
「ほら、座って」
「あ、あの、でも私」
「花見の時期だったら良かったんだけどねえ」
手を引かれ、並んで腰を下ろす。
でも、と言いながらも外に出られて千鶴はほっとしていた。
頬を撫でる風は冷たいが、部屋の中にいるよりもずっと気持ちが晴れやかになる。
「はい、もひとつ」
金平糖をもう一つ差し出された。今度は千鶴も遠慮しなかった。
「いただきます」
「どうぞ」
一粒掴んで、口の中に放り込む。
ふわとまた広がる甘い香りと、冬の風の冷たさを感じながら、ちらりと千鶴はそっと隣に座る彼女を盗み見た。
良い天気だなと呟いて空を眩しげに見上げている彼女は、酷く美しかった。
最初に見た時はそれどころではなかったが、改めて見るとこれほど造形の美しい人がいるのかと驚かされるばかりの美貌である。
陶器のような滑らかな白い肌も、切れ長の琥珀の瞳も。薄い唇も、通った鼻筋も、顔の輪郭も全て人形のように完璧で、美しい。
「ん?」
視線を感じたのだろう。がこちらを振り向いた。
「あ、いえっ」
慌てて視線を逸らすと、は目元をすいっと細めて悪戯っぽく笑ってみせた。それはそれは色っぽい笑みに、どきりと千鶴の胸が高鳴る。
一種の恋心を、この時の千鶴はに抱いていた。
彼女が女であると知らない千鶴にとって、という存在は想いを寄せてしまう程に魅力的な存在だったのだ。
「はい、残りあげる」
包みから二つ程拝借すると、は残りを千鶴の手に持たせた。見ればまだまだたくさん残っている。
「え、でも、こんなにたくさん、」
が貰ったものなのに、こんなに貰ったら申し訳ない。
千鶴は言って返そうとしたけれど、その手を上から優しく包まれて思わず硬直してしまった。どきんっと鼓動が跳ねたのが分かった。
「余ったら、今度平助と一緒に食べればいいよ。喜ぶと思うから」
優しく笑い、はその手を離す。
千鶴はまた、と思うのだ。この笑顔には逆らえない。
この優しさには、甘えずにはいられない。
狡いなぁと心の中でだけひっそりと呟いた。
こんなに優しくされると錯覚してしまうのに。今の状況を忘れてしまいそうになるのに。
「ありがとう、ございます」
申し訳なさそうに、しかし嬉しそうに目元を綻ばせて頭を下げる千鶴には満足げに頷いた。
そうして視線をまた庭の方へと向ける。
「そう言えばさん……お仕事は落ち着いたんですか?」
千鶴は包みを懐にしまい込みながらふと、その横顔に問いかけてみた。
が忙しい、というのは千鶴もよく知っている。何をしているのかは知らされていないが、この屯所に来てから彼女が毎日のように仕事で走り回っている聞いていた。夕飯時にの姿がなかったことは何度だってある。
「あいつは仕事が多いんだ」
と呆れ顔で藤堂が言っていた。
明け方まで帰ってこない日もざらではないのだと。
それに、今は土方が大坂に行っているので彼女の仕事は更に増えたとも言っていた。どうやら彼の仕事を代わりにやっているらしい。ただでさえ忙しい上に、彼の仕事もこなしているのでは大変だろう。
問いかけには苦笑した。
「うん、まあ、昨日まではちょっと大変だったかな」
「……」
そんな大変な状況だというのに、彼女はわざわざ来てくれたのだ。
有り難い以上に申し訳なくて千鶴は表情を曇らせる。話し相手になってくれると喜んだ自分が酷く恥ずかしかった。
「そんな顔しなくても平気だよ」
は優しい一言と共に、ひょいと顔を覗き込んでくる。
瞬間、いつもよりも近付いた瞳に一瞬にして囚われた。澄み切った琥珀は光を浴びてきらりと黄金色に輝いたように見えた。なんて綺麗な色なのだろうかと千鶴は思ったものだ。
「実はね……土方さんに、君の事を頼まれているんだよ」
美しいの顔が、困ったように表情になる。
千鶴は小首を傾げた。
土方に頼まれている? 何を?
きょとんと目をまん丸くするそれだけで彼女が何を問いたいのかが分かった。は困ったような顔で、それから何故かその眉根に思い切り皺を刻んだ。千鶴の前ではあまり見せない顔だった。
「やあ、。何楽しそうな事してるの?」
――唐突に、の言葉を声が遮った。千鶴ではない。
え、と小さく彼女が声を上げればやはり同じように突然、覆い被さるように影が重なる。ぽかんとした顔を上げれば、意地悪な翡翠が見下ろしていて、
「お、沖田さ――っ!?」
驚いた拍子にずるりと手が滑った。そのまま縁側を滑り落ちて無様に庭に尻餅を着いてしまいそうになる。
「っと」
それを、腕を掴んで支えてくれたのは勿論であった。
「大丈夫?」
「は、い、す、すみませ……」
心臓がどきんどきんと痛いくらいに強く、早く、鼓動を繰り返している。突然彼が現れた事もそうだが、それに加えて縁側から落ちてしまった事も彼女の動揺を強くしているのだろう。胸を押さえて呼吸を整えようと必死の様子だ。
「ごめんね。うちにはああいう馬鹿な事ばっかりする悪ガキがいるから、くれぐれも気をつけるようにって言われてたんだけど」
早速馬鹿をしに来たみたいだね、とは千鶴の頭をよしよしと撫でながら謝ってくれる。
別にそんなのが謝る事ではない。そう言いたいのにまだ心臓が暴れていて上手く言葉に出来ない。仕方ないので千鶴はふるふると必死に頭を振る事で意志を伝えれば、それを汲み取ってくれたのかの手が更に優しく頭を撫でてくれた。
「……で? いつまで笑ってるつもりかな? 悪ガキ代表総司君」
因みに――沖田は先程から腹を抱えて爆笑中である。
どうやら千鶴の反応が彼のツボに入ったらしい。大声で馬鹿笑いをする沖田を些か冷たい目で見れば、彼はひいひいと苦しげな声を漏らしながら涙を拭った。
「泣く程笑う奴があるか」
「だ、だって、縁側から落ちるとか、おかしいでしょ」
「それはおまえが驚かしたからだろ。わざわざ気配を殺して後ろから忍び寄っていたいけな少女を驚かすなんて、立派な男がやる事か」
「だって、仕事中の土方さんを大きな音を立てて驚かせてたりするじゃない」
「あの人は良いの。悪戯しても堪えないから」
それを土方当人が聞いたらどんな顔をするだろう。まあまず拳骨を落とされるのは確かだ。どっちもどっちだと。
「それにしてもさ、そんなに驚く事もないんじゃない?」
ひとしきり笑った後、沖田は意地の悪い顔でこちらへと近付いてくる。
漸く落ち着いた千鶴はそれにまたぎくっと肩を震わせ、硬い表情で彼を見上げた。そんな素直すぎる反応に沖田は内心で笑い、その顔に悲しみを浮かべた。
「身構えなくても良いじゃない。そんなに僕が苦手?」
傷つくなぁとわざとらしく呟けば、この心優しい少女が慌てて否定をしないわけがない。
「す、すみません! そうじゃないんです! ただ、ちょっとびっくりしてしまって」
「とてもびっくりしただけとは思えない反応だったけど。まるで幽霊とか鬼の副長に出会ったみたいな反応だったよ?」
「幽霊と鬼の副長は同列か。せめて生きてるもんと同じにしてやれ」
が冷静に突っ込んだが沖田は華麗に流す。ここで反応をしては台無しだ。
彼は一層傷ついたという表情で溜息混じりに呟いた。
「僕の事、そんなに怖いの?」
「あ……」
千鶴ははっとしたような表情になり、それから申し訳なさそうに俯いた。
確かに彼の姿を見た瞬間驚いたが、同時に警戒もしてしまった。出会いが悪かったせいもあり、彼が意地悪な言葉でからかってくるせいもあり、少々苦手だと感じてしまっているのも確かだろう。それがもしかしたら表に出ていたかもしれない。だとしたら彼にはとても酷い事をしてしまったのではないかと思う。いくら苦手な相手と雖も、あからさまに嫌がるような反応は良くない。自分がされてしまったら悲しくて堪らない。
「総司、あんまり千鶴ちゃん苛めるな」
このままでは千鶴の方が謝りかねないので、はもう一度口を挟んで間に割り込む事にした。
「おまえみたいな物騒なヤツ、怖くないわけがないだろ」
「鬼副長の右腕にまで怖いって言われたら、僕傷ついちゃうなあ」
「こんな事くらいで傷つくような繊細な心持ち合わせないだろうが」
「ひどい言い方。ねえ、千鶴ちゃんも思わない?」
ひょいと肩を竦めてみせる彼は悪戯っぽい表情を浮かべている。
先程まで見せていた悲しそうな表情はどこにもない。まさか全て嘘だったのかと驚愕に目を見張れば、彼はにこりとその目を細めて気まぐれな猫のように笑った。
そしてもう興味が失せたのか、何でもなかったみたいに顔を庭の方へと向けるとどっかとの横に腰を下ろす。
「良い天気だよね」
「って、こら何仕事サボってんだ」
暢気に言ってそのままごろんと縁側に寝ころんでしまいそうな男をは窘める。
「今日はおまえが隊士の稽古つける番だろ?」
「だってがいなくてつまんないから、一君に代わってもらった」
つまらないから、という理由だけで稽古を抜けてくるとはどういう事か。これでも一番組の隊士を束ねる組長だというのだから呆れてしまうというものだ。
「あのね、私の稽古をつけるんじゃないでしょうが。ってか代わってもらったじゃなくて、押しつけたの間違いだろ?」
「そうとも言うね。あ、が来てくれるなら戻ってもいいよ?」
「生憎と私は千鶴ちゃんとのんびりしてる」
「じゃあ僕も」
「おまえがいるとのんびりできない。だからとっとと戻れ。邪魔するな」
「邪魔だなんてひどいなあ」
ひどい、と言葉にしながらも沖田の表情はとても楽しそうに見える。
否、実際楽しくて仕方ないのだろう。
彼らはその言葉でじゃれあっているのだ。言葉で戯れるというとなんだか不思議な気がするが、二人の会話を聞いていると戯れあっているように聞こえる。お互いに自分の言葉で相手がどう反応するのか楽しんでいる。だから時々ひやりとするような言葉も挟んでくるのだろうか。その辛辣な言葉の反応さえ楽しむかのように。
恐らく、仲が良いのだろう。でなければこんな風にはならない。
じゃれ合うみたいな言い合いや、土方に対する時の息のあった抗議。端から聞いていてひやりとする辛辣な言葉や、乱暴な物言いも、仲が良いからこそ出来るのだろう。
いや、違う。仲が良いだけではない。この二人の間には何か個々の人間という境界線を感じない。まるで二人は一つのもので出来ているかのような――無論、赤の他人である彼らが一つのものであるはずがない。けれども確かに千鶴にはそう感じられた。
『あの二人は似ているんだよ』
ふと、近藤が言っていた言葉を思い出した。
何故かそう告げた彼の顔は少し悲しげだった理由を、彼女は知らない。
『あの二人は似ているんだよ』
ただ、その言葉の意味が分からずに首を捻っただけだった。
次 頁
|